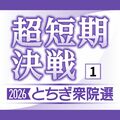高校受験は誰でもできる-。それが当たり前でない状況をも、貧困はもたらす。
98%を超える県内の高校進学率。なのに、本紙調査によると、生活保護受給家庭の子では84・2%にとどまっている。
その差約15ポイントの中の子に何が起きているのか。
母親が深夜まで働き詰めで、弟、妹と子どもだけで過ごす不安から、勉強が手に付かない祐汰君。第2章で取り上げた県央の中学2年生。
学費が高い私立高には進学できない。「県立高に合格しなければ、高校に行けないかも…」。不安が強まった。「勉強しても仕方がないのかな」
塾に通う余裕もなかったから、母親から「ボランティアが勉強を教えてくれる場所がある」と聞き、即答した。
「行くっ」
学習支援を受けて「勉強が分かる」と感じられ、「頑張れそう」と思えるようにもなった。
宇都宮市の父子家庭に暮らす16歳の少年。定時制高に進もうとしたこともあるが、高校には通っていない。進学のことなど頭にないように、求人情報誌をめくり続けた。
本年度、県内7市町で始まる学習支援。学ぶ意欲を支えるため、速やかに全市町で行うべきだ。
◇ ◇ ◇
「結局、お金がないと、どうにもならないじゃないですか」。県北でアルバイトを掛け持ちし家計を担う由衣さん(仮名)は記者に言った。定時制高3年だった。
全日制高も合格圏内だったのに、ひとり親の母は制服代などが払えなかった。定時制高に入り「進学のため」と寝る間も惜しみ働いて、心身ともに追い詰められた。
授業料を払えず、私立高を卒業目前で中退した宇都宮市の女子生徒もいた。
政府総支出に占める教育費の割合は、先進諸国で最低水準。その分、家計に負担がのしかかる。
◇ ◇ ◇
第6章の取材。子どもの貧困対策の先進地、英国を訪れた。
「教育は貧困の連鎖を断ち切る」。こうした意識が対策に携わる人々に共通していた。だから、戦後最大の財政赤字を抱える今も教育費だけは削っていない。
「覚悟」を感じた。
小中学生に学用品代などを補助する日本の就学援助制度。「三位一体改革」で国の補助が削減され、市町間に格差が生まれている。
大学生なども含め奨学金は給付、無利子型は少なく、有利子型が増え続ける。「必要な時に間に合わない」という声も絶えない。
母子家庭を支援する宇都宮市の宮路順子さん(58)は願う。「どんな方法でもいいから、子どもが学校に行けるように」
教育への投資は将来への投資。その枠組みづくりは急務だ。

 ポストする
ポストする