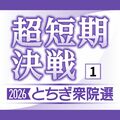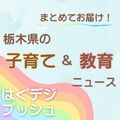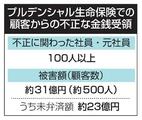呼び鈴を鳴らしても、誰も出てこない。
2012年春。県北の自治体職員村上京子さんは母子4人の住むアパートに通い始めた。養育が難しい家庭の相談員。支援しようとしている家の母親は自分の子どもと同年代だ。
車は駐車場に置かれ、洗濯物は干してあった。
何度目の訪問だろう。ようやく玄関の扉を開けたのは男の子。どうやら、中学3年生の次男亮太君のようだ。
着古したランニングに短パン姿。顔色は悪く、やせている。
「食べてないんだろうな」と思いつつ、尋ねた。「お母さん、いる?」
亮太君はにこにこしながらも首をかしげるだけ。中のことは、うかがえない。
1週間後、再び訪ねると、また亮太君が現れた。顔色は相変わらずすぐれず、服装も同じ。
「着る物がないのかな。それにしても…」。亮太君のいでたちは、肌寒い日でも変わらなかった。「外に出ていないのだろうか」
親子の情報を同僚から引き継いでいた。
36歳の母親は失業中。生活は苦しく、電気、ガス、水道が止められることもある。16歳の長男は高校に進学していない。亮太君と小学6年生だった三男は、学校から遠ざかっている。
暮らしぶりが分からない。足しげく通った。
母親には会えていなかった。長男がいるのは分かる。でも姿は見せない。
何度も呼び掛けて、やっと冷蔵庫の影まで出てきた三男。目を合わせようとはしなかった。
亮太君に話を聞こうとしても、蚊の鳴くような声。
「もしかして人と話をしていないんじゃ…」。事態の深刻さに胸を突かれた。「この子たち、このままだと、社会に出られない」
◇ ◇ ◇
親子は05年まで、生活保護を受けて県内の母子生活支援施設にいた。
入浴時間などが決められ、ルールに縛られた暮らし。その年の夏、窮屈さを感じた母親香織さんは、県北のアパートに引っ越した。長男が小学4年生の時だ。
飲食店のパートで働き始めてすぐ、車のない生活に限界を感じるようになった。通勤も、三男を保育園に送るのも自転車。
どうしても車を手に入れたくなって、自ら生活保護から抜けた。
手にした自由。引き換えに困窮に追い込まれる。
保護費がなくなり月収は10万円ほどに減った。家賃だけで4万3千円。年3回支給される児童扶養手当は滞納した支払いに消える。
「すべて1人でやらなきゃ」。心のゆとりは失われていった。
施設では、香織さんが外出しても面倒をみてもらえた子どもたち。その子たちが家に引きこもるようになる。孤立は深まっていく。
(文中仮名)

 ポストする
ポストする