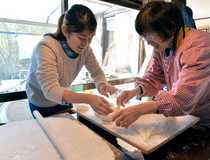当たり障りのないはずの会話におびえ、ずっとうそをついてきた。
自らのせいでないことは分かっていた。「でも、そんな自分がかわいそうに思えて…」
児童養護施設で育った宇都宮市内のNPO法人職員の塩尻真由美さん(32)は、自立しひとり暮らしを始めた。26歳になっていた。化粧品販売会社での仕事も充実していた。
高校卒業後、就職。社会に放り出され、崩れ落ちそうになった。元施設職員の石川浩子さん(53)に手を差し伸べられ、7年間一緒に暮らした。
◇ ◇ ◇
化粧品販売の仕事でのやりとり。お客さんは、真由美さんの親世代が多い。
「お母さんて、何歳ぐらい?」
尋ねられるたび、こう答えた。
「お客さまと同じくらいですよ」「一緒に買い物にも行きます」
必死に普通の家庭で育った自分をつくり上げた。
「施設出身」と言いたくない。親に必要とされないことが寂しく恥ずかしく、同僚にもひた隠しにした。
好きな人にだけはうそをつきたくない。付き合いだしてまもないころ、打ち明けた。
「おれも自分の家しか知らないし、普通かどうかも分からない」
彼は、笑って受け止めてくれた。
この人となら自然でいられる。交際は6年間に及んだ。
意識し始めた結婚。祝福されるはずの挙式を考えると、気がめいった。
来てくれる人に、「施設出身」をどう伝えるの。それとも伝えないの?
彼の両親は温かく受け入れてくれたが、親戚はどう? 招待客の肩書は。好奇の目にさらされないか。
石川さんは「新婦の母親として出席してもいい」と言ってくれた。
◇ ◇ ◇
でも-。これ以上うそはつきたくない。
同僚たちに結婚式の招待状を渡す時、意を決して打ち明けた。
みんな驚き、店長は涙声で言った。「どうして話してくれなかったの。聞いたって、何も変わらないよ」
思いがけない言葉だった。
2011年の結婚式。施設関係者は「恩師」の肩書で出席した。石川さん手作りのウエディングベールをまとい、バージンロードは施設の元職員がともに歩いてくれた。
「おめでとう」。あちこちから上がる祝福の声。
背負わされ続けた荷物を下ろした自分が、そこにいた。

 ポストする
ポストする