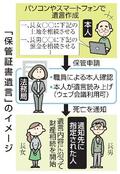衣食住すらままならない日々を越え、つかんだ春。
3月12日。午前10時ちょうど。
まだ雪が残る県北の県立高の一角で、合格者の受験番号が掲示された瞬間、小さく声をあげた。

「あった」
県北の中学校に通う佑樹君(15)=仮名=が、左腕にしがみついた母親(40)と顔を見合わせる。
かつては入試に挑戦することなど考えもしなかった自分が、全日制普通科に合格できた。「信じられない」。目を見開いた。
小学校低学年から、「学力」を理由にいくつかの教科の授業を特別支援学級で受けた。
「もともとは普通に力のある子」
佑樹君の生活支援をしている日光市のNPO法人「だいじょうぶ」代表の畠山由美さん(53)はそう感じてきた。
「子どもが普通に育つ環境がない」
兄と妹がいる母子家庭。幼いころから生活保護を受けて暮らした。保護費は月十数万円。しかし、支給された途端、滞納した家賃の支払いや母親が家族の服を買い込んだりし、すぐに底をついた。
母親は家にいたが、十分に家事ができなかった。
◇ ◇ ◇
佑樹君が小学6年生になった2010年春。4歳上の兄は定時制の高校生、妹の奈津美ちゃん(10)=仮名=は小学校に入学した。
真新しいランドセルを背負う奈津美ちゃん。1年生になっても、オムツを外せないでいた。
トイレは、家にないも同然だった。
水道料金の支払いが滞り、水は出ない。トイレットペーパーもない。奈津美ちゃんは、トイレに座ることも知らなかった。
家に飲み物がなければ、子どもたちは近くの公園の水道でのどを潤した。佑樹君は便意を覚えると、公園のトイレに向かった。
静まり返る夜の公園。蛍光灯がつかず、兄にドアの前にいてもらい用を足す。
「そこにいるよね、ね」
不安だから、ずっと話しかけ続けた。
壮絶な暮らしは、佑樹君たちから分別さえ奪った。
空腹に耐えかね、妹と一緒に近所の店の食料や菓子を黙って食べ、牛乳も飲んだ。「学校なんて、どうでもいい」と思ったが、おなかがすくから給食前には登校した。
このころ、畠山さんは佑樹君たちの窮状を知った。
支援者との出会い。きょうだいや母親に、変化をもたらしていく。
◇ ◇ ◇
経済的困窮の中、毎日の衣食住が脅かされている子どもがいる。基本的な生活習慣や学力が身につかない。不登校になることも、いじめに遭うこともある。やがて、社会とのつながりを持てなくなり孤立する。幼いころから貧困にさらされるほど、困難は積み重なる。第3章は、手を差し伸べる支援者、そのかかわりから変わっていく子どもの姿を追う。

 ポストする
ポストする