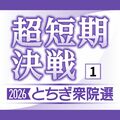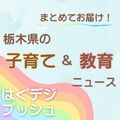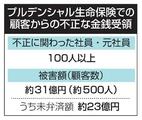カレーライスが二つ、食卓に並ぶ。
日が暮れるころ。東京・足立区の山本恭子さん(63)=仮名=が、区内の小学校に通う低学年の児童のため、腕を振るった。
保護者の事情で夜、一人の時間を過ごす児童。
山本さんが家を訪れ、世話を焼く。学校の話に相づちを打ちながら一緒に食べた。
帰る時、児童は「また待ってるね」と言ってくれるようになった。
この家には、2013年春から区の「協力家庭」として通っている。
地域の中でわが子3人を育てた山本さん。児童のことは、区から「ぬくもりのある家庭の味を作ってもらえませんか」と頼まれていた。
◇ ◇ ◇
協力家庭による「あだち・ほっとほーむ事業」は02年度に始まった。有償ボランティアである協力家庭は元保育士ら約90人。
区は保育園への送迎、学童保育後の一時預かりなどのファミリーサポート事業も行っている。「食事の提供が必要だったり、ファミサポでは支援が足りない家庭もある」と区こども支援担当課の富山耕生さん(36)。
養育が難しかったり、経済的に困窮する家庭が対象になることが多く「子どもそれぞれに合った支援を見極め、協力家庭に橋渡しする」。
主任児童委員などとして長年、地域の子どもとかかわってきた山本さん。困窮する子どもの存在は分かっても、「ご飯、作ろうか」と言い出すのは難しかった。
ずっと感じていたもどかしさ。ほっとほーむ事業が、行き場のない思いを子どもにつないでくれる。
◇ ◇ ◇
宇都宮市内。
門馬芳子さん(63)はひとり親の困窮家庭で暮らすきょうだいを支援している。アパートを訪ねて食べ物を届け、ともに調理し、たまには一緒に食卓も囲む。
自分を「ただの世話好きのおばさん」と言う。ボランティア団体の活動に触れ、支援に携わるようになった。
1年半以上、きょうだいにかかわる中で感じている。「困っているのはきっと、この子たちだけではない」
最近、仲間と一緒に衣食住の面倒を見る「居場所」を作りたいと思うようになってきている。
場所の当てはある。人手も何とかなる。ただ困っている子どもがどこにいるのかが分からない。
「同じように思う人って、結構いるんじゃないかな」
子どもを包み込む地域の力。その萌芽は県内にもある。
(第4章終わり)

 ポストする
ポストする