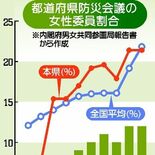能登半島地震や阪神淡路大震災、東日本大震災など災害時にはトイレ問題が取り上げられた。災害時のトイレ事情に詳しいNPO法人県防災士会理事の中川享子(なかがわきょうこ)さんは「避難生活でトイレは自分一人になれる唯一の場所にもなる。感染症や関連死のリスクはもちろん、心身の健康にもつながるものとして対策を進めてほしい」と強調する。
中川さんによると、排せつのタイミングや回数は個人で異なり、我慢が難しい。排せつを少なくしようと水分や食事を制限し、体を動かさないようにすると、エコノミー症候群や心筋梗塞、脳梗塞など体調不良を引き起こす可能性や、震災関連死につながるケースもある。水道が使えず排せつ物がたまると、トイレや周辺の衛生環境が悪化し、感染症が拡大するリスクもある。

断水時でも使える設備として(1)凝固剤で排せつ物を固める「携帯トイレ」(2)ベンチなどの形で持ち運びができる「簡易トイレ」(3)平常時に工事現場やイベント会場で使われる「仮設トイレ」(4)下水道管とつなげた専用マンホールに設置する「マンホールトイレ」-などがある。
能登半島地震の被災地は交通網が寸断され、トイレを届けるのに時間がかかった。中川さんは避難所のトイレ状況を把握し、対応を進める行政担当者は必要として「交通網のまひなどを見越し、普段から数種類のトイレを備えておくべきだ」と指摘している。

 ポストする
ポストする