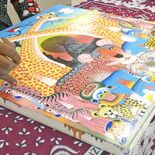消防車や警察車両の展示のほか、応急手当てや通報などの体験コーナーが設けられ、多くの人でにぎわった。同署の山口裕隆(やまぐちひろたか)副署長(56)は「本県が被災した東日本大震災からかなり経過し、どうしても防災意識が薄くなる。改めて防災について考えてほしい」と開催の狙いを語る。
■ ■
オリオン通りで倒れている人がいた際、居合わせた人には何ができるか。応急手当てコーナーではそのような想定で、胸骨圧迫による心臓マッサージと自動体外式除細動器(AED)の使用を体験した。まずは肩を叩きながら耳元で「分かりますか」と3回声をかける。反応がなければ大声で「誰か来てください」と周囲に助けを求め、救急通報とAEDを持ってくるよう依頼する。6秒間胸の動きを見て、上下していなければ呼吸が止まっている。心臓マッサージが必要だ。

重ねた手の付け根を両胸の中央に当て、1分間に100回のペースで救急車到着まで押し続ける。胸が5センチほど沈む強さが目安で、思ったよりも力がいる。「うまいですよ」と褒めてもらったが、救急車到着までの平均7、8分間続けるのは大変だ。周囲の人と交代でマッサージするのも効果的だという。
AEDは電源を入れると流れる音声メッセージに従い、2枚のパッドを所定の位置に貼り付ける。後は体に触れていないのを確認し、ショックを与えるだけだ。初めてでも簡単に操作できた。
■ ■

建物火災を想定した対処法も体験した。煙体験テントに入ると、立ったままでは煙で何も見えない。アドバイスを受けて姿勢を低くし、壁を手で探ると何とか前に進むことができた。消火器を使った初期消火では職員から「飛距離は5メートル、噴射時間は15秒」と教わった後、消火までの一連の流れを実践した。

市消防局が2022年から導入している映像通報システム「Live(ライブ)119」の体験会も開かれた。スマートフォンで119番通報すると、司令員が必要に応じて専用URLをショートメッセージサービス(SMS)で送信する。通報者がアクセスすれば動画を送受信できる。この日は倒れている人を発見した想定で通報し、心臓マッサージ手順の動画が送られてきた。通報者から動画を送信することも可能だ。動画は出動隊にも共有され、迅速な対応に生かされる。
■ ■
災害の現場では冷静さを失いがち。過去には炎に消火器を投げ入れてしまった人もいたそうだ。事前に対処法を学び、実際に体験してみることは大切だと感じた。次回も災害への備えについて考えます。
 ポストする
ポストする