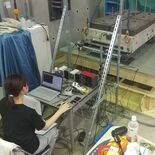県内には世代を問わず、多くの防災教育の取り組みが行われています。文部科学省委託事業として県教委が実施している「学校安全総合支援事業」において、本年度はさくら市押上小を拠点校に、地元の消防団や防災士と連携した避難訓練や避難所体験が行われています。また理科や社会の時間には、自然災害を関連付けた学習にも取り組んでいます。
このほか、同事業では、市内各小中学校をモデル対象校に指定し、学校規模や地域特性に応じた防災教育を推進しています。児童生徒数によっては実施内容が限定的になることが懸念されるものの、地域の人材や団体とつながった豊かな実践が期待されます。
防災教育は学校教育だけでなく、成人が対象の社会教育としての取り組みも見て取れます。宇都宮大では、県危機管理防災局の協力を得て、県内市町が昨年度実施した地域住民向け防災研修の実施状況についてアンケートを行いました。詳細な結果は分析中であるものの、24市町であわせて236件の研修について報告が寄せられました。その対象だけを見てみても、自治会や自主防災組織などの地域住民組織をはじめ、福祉団体や子育て世代など、実に多様です。
宇都宮大では、本年度の「さくら市民大学」として実施した防災リーダー養成講座についてプログラム開発の支援を行いました。全7回の講座は、本学教員や県内活動実践者、市職員が講師となり、ハザードマップの見方や災害後の心理的問題、災害弱者の存在について学ぶ内容としました。
一方的な情報提供に終始せず、講師陣の専門的な知見と参加者の日々の暮らしをひも付けられるよう、参加型学習を織り交ぜている点が特徴として挙げられます。講座最終回では、学びを振り返るために「自分がこれから取り組むこと」を参加者一人一人が発表しましたが、「あいさつから始める地域のつながりの拡充」「近隣世帯(班)の家族構成の確認」などの声が上がりました。
「地域の知の拠点」として、宇都宮大はさまざまな学習ニーズに寄り添うための取り組みを推進しています。地域防災については、防災士をはじめとする実践者向け応用教育プログラムや、学生と共に学ぶ「UUカレッジ」における関連科目の拡充を行う予定ですので、引き続きご注目ください。

◆つちざき・ゆうすけ◆
宇都宮大地域デザインセンターコーディネーター。専門はボランティア・NPO論で、主に災害ボランティアの活動支援に従事。とちぎ市民協働研究会専務理事、宇都宮まちづくり市民工房常務理事。社会教育士、防災士。
地域防災シンポ 宇都宮で来月1日
宇都宮大は12月1日午後1時~4時半、地域防災シンポジウムをJR宇都宮駅東口の交流拠点施設ライトキューブ宇都宮で開く。県内で防災活動を実践する団体や専門家の取り組みを学ぶ。
参加無料。定員200人。27日までに専用フォーム(https://forms.office.com/r/etMktbawug)から申し込む。(問)地域デザインセンター028・689・6235。


 ポストする
ポストする