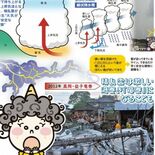県内で4人が死亡し、1万4千棟余りの住宅が被災した2019年の台風19号から12日で4年となった。被害を機に議論が本格化したのが、地域住民がまとまって安全な場所に移り住む「防災集団移転」。市町が担う促進事業は那須烏山市と小山市で進んでいるものの、道半ばだ。1972年に始まった促進事業で移転を完了した全国の自治体はこれまでに延べ35市町村(東日本大震災の被災地を除く)にとどまり、住民の合意形成などが課題となっている。
同事業は災害で被害を受けた地域や、将来被災する恐れのある地域が対象。自治体が移転先の宅地を整備し、国が補助する。
那須烏山市は20年に「防災集団移転」の検討を始めた。対象は台風19号で被災した下境地区69世帯と宮原地区39世帯で、既に移転先の候補地を示し、意向確認を行っている。市は本年度中にも国から事業計画の同意を得たい考えで、10月中に国との調整に着手できるよう目指す。
ただし、課題もある。国の事業を活用するには、原則として対象区域全世帯の移転への同意が必要になるためだ。市の担当者は「住民の希望を最大限踏まえつつ、どうすれば国の要件を満たせるかを考えている。一番高い壁に向き合っている状況だ」と話した。
小山市では15年の関東・東北豪雨や台風19号などで水害に見舞われた押切地区の住民有志が21年、集団移転を求める要望書を提出。市は対象の約30世帯からおおむね参加の意思を得ており、25年度に国から同意を得ることを目指す。
一方、茂木町は20年に国が公表した「那珂川緊急治水対策プロジェクト」で集団移転が選択肢の一つに示されたが、移転の希望者数が国の条件に届かないことなどから「保留」としている。
国土交通省によると、災害で被災した地域の再建で集落が集団移転した例はあるものの、災害が起きる前の「事前防災」として移転が完了したケースはない。那須烏山と小山はこの事前防災に当たるという。
移転のハードルを下げるため、同省は20年度に集団移転先の住宅団地の規模に関する要件を「10戸以上」から「5戸以上」に引き下げるなど、要件緩和に乗り出している。同省の担当者は「災害が激甚化する中、堤防の整備などのハード面だけで対応は難しく、事前防災の重要性は高まっている」と説明した。
 ポストする
ポストする