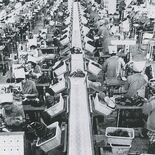栃木市北部の西方町本城にある取水堰(せき)「小倉堰」。「ゴー」という音と共に、川の水が堰を通って流れていく。夏季にはアユを求める釣り人の姿も見られ、涼やかな景観が広がっている。
小倉堰土地改良区の担当者は「堰は1954年に完成したものが土台となり、現在の形になっている」と説明する。堰で取水された水は水路を通り、西方地区の農業用水や生活用水として使われるなど現在も重要な役割を果たしている。
西方の大地を潤す小倉堰は、江戸時代から改修の歴史を繰り返し、現在まで守り築かれている。同改良区や西方町史によると、約400年前の江戸時代初期、当時の西方城主が築いた農業用の堰が前身とされる。当時は川の中にくいを打ち、竹で編んだ籠の中に石を詰めた蛇籠(じゃかご)で堰を造った。
1700年ごろは長さ約200メートル、高さ約1・5メートルだったとされ、「西方五千石」と呼ばれた西方地区の稲作を支えた。ただ、頑丈な構造とはいえず、洪水など自然災害などで破損し改修工事が繰り返された。
明治、大正期にも洪水によって取水不能になることがあり、地元住民からより強固で近代的な堰を求める声が上がる。1951年に始まった造成工事により、現在につながる姿になった。築堤から約60年経過した2010年の調査では、護床工ブロックの劣化や漏水などが判明。これらを補修し長寿命化を施す工事が17年に始まり、21年に完了した。
小倉堰の南側にはバーベキュー広場や遊具、運動公園を備えた西方ふれあいパークが整備され、地元住民の憩いの場としても親しまれている。

 ポストする
ポストする