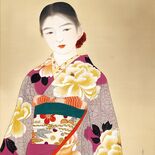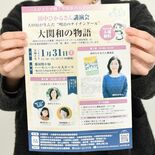矢板市の秋の味覚といえばリンゴ。19軒が計24・3ヘクタールを栽培し、県全体の17%を占める。流通の8割は直売で、各リンゴ園には樹上で完熟した果実を求め、多くの観光客が訪れる。
市内栽培の歴史は約1世紀前にさかのぼる。市史には1914(大正3)年、山県(やまがた)(有朋(ありとも))公が青森県から技師を招いてリンゴの苗木を植栽、40年ころから、何人かが収穫を始めたとある。苗木の植栽場所は山県農場内、現在の山縣(やまがた)有朋記念館(上伊佐野)辺りのようだ。
何人かの収穫者の一人、故小野平二郎(おのへいじろう)さんの長男勝彦(かつひこ)さん(85)=下伊佐野=は「農場のリンゴを見て、ここでもなると父が福島県で苗木を買い付け、分けてあげた」と説明。栽培者は地区内に広がり、数軒が残ったという。
12軒の観光リンゴ園が集中し生産地・矢板を代表する長井地区の植栽は47年、出征中に知り合った山形県のリンゴ農家に触発された故加藤久一(かとうきゅういち)さんが始めた。
同時代に生き地区も近い加藤さんと平二郎さんは市果樹生産出荷組合を設立するなど共に産地形成へ尽力。宇都宮などの市場で苦戦したが“リンゴの王様”ふじの生産に適した土地が幸いし、直売式が定着した。
課題は生産者の高齢化、後継者不足だ。同組合が前身のJAしおのや矢板果樹部会長の荒井貴良(あらいたかよし)さん(60)=長井=は「大規模化する所が辞める農家を救っていけるか」を鍵に挙げる。7年前、農園を法人化した加藤さんの長男隆重(たかじゅう)さん(76)=同=は「地域が豊かになることが父の夢だった。業界全体で若い人を増やしていければ」と前を向く。

 ポストする
ポストする