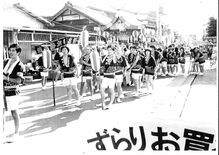「ウー」。岩船山から鳴り響くサイレン。次の瞬間、発破音が一帯にとどろく。麓からは岩舟石を積んだダンプカーが地面を揺らして続々と出発していく-。
昭和30(1955)年代の栃木市岩舟地区(旧岩舟町)は活気にあふれていた。「うるさかったけど、それが日常。石が岩舟の経済を支えてくれていた」。山麓にある「岩舟石の資料館」の管理人加藤千代(かとうちよ)さん(67)が往時を懐かしむ。
岩舟石は標高173メートルの岩船山から産出される凝灰岩の一種。水や火に強く、加工しやすいのが特徴だ。江戸時代に採石が始まり、主に城や社寺の石垣や石段に使われていた。
明治に入ると、建物や護岸工事などへの需要が増す。150年前、同市(当時は栃木町)に置かれた初代県庁舎の土台や堀にも採用された。文字通り本県の発展を下支えしたといえる。
荷車や馬車だった運搬方法も発達した。1900年には人が貨車を押す人車鉄道が渡良瀬川まで開通。代わって18年に規格が簡便な軽便鉄道も一時敷設された。その後は両毛線や東武日光線、トラックが輸送を担った。
戦後は建築ブームに湧いた。最盛期だった55年ごろの石材店は36を数え、1日200台以上のダンプカーが行き交った。だが60年代からコンクリートが主流となり、需要は激減。砕石で生き残りを図った業者も相次いで撤退し、平成に入って姿を消した。
盛衰をたどった岩舟石が建材の役目を終えた一方、採石場跡地は70年代後半から、映画やドラマのロケ地として人気となった。地元有志が始めた野外コンサート「岩船山クリフステージ」も今年20回の節目を迎え、まちおこしに一役買っている。

 ポストする
ポストする