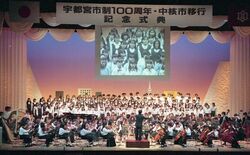江戸時代末期、現在の那須町には黒羽藩領、参勤交代を行う旗本「交代寄合」だった芦野氏の支配地、幕府の直轄地(天領)が存在した。1889年の町村制施行により、芦野町、伊王野村、那須村が誕生した。1920年の人口は計2万64人だった。
40年には2万3069人となり、終戦後には第1次ベビーブームに加え、旧満州(中国東北部)からの引き揚げ者らが続々と入植した影響でさらに増加。50年には3万1241人とピークに達した。町村合併促進法の施行を受け、54年11月には1町2村が合併し那須町が誕生。黒磯町(旧鍋掛村)寺子のうち黒川地区が編入され、現在の町域となった55年には3万1034人となった。
町中心部にあるJR黒田原駅前で父親の代から書店を営む金子弘行(かねこひろゆき)さん(68)は、55年当時の同駅前通りのにぎわいを伝える写真を多数保存。「当時は車を持っている人も少なかったから、みんな黒磯町(現那須塩原市)の工場などへの通勤や通学に電車を使っていた。この通りも朝と夕方は乗降客がすごかった」と懐かしそうに振り返った。
60年代以降は緩やかに減少し、90年には2万6670人に。2000年には2万7千人台に回復したが、今年4月1日現在で2万3344人。高齢化率は40%を超えている。

 ポストする
ポストする