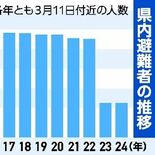廃炉への道は長く 構内埋め尽くすタンク
JOD「#311jp」記者講座の参加者は2月26日、東京電力福島第1原発に入った。
2018年から、構内の約96%で防護服の着用は不要になった。1日平均4500人の作業員が働き、その約7割が福島県民だ。

構内のいたる場所に千トン級のタンクが並ぶ。海洋放出を待つ原発処理水だ。見学用の高台に上ると、100メートル先に水素爆発を起こした1号機の姿が見える。壁は剥がれ、鉄骨はむき出しだった。建屋内に残る溶融核燃料(デブリ)の試験的取り出しは、作業の開始延期が続く。全ての廃炉作業を完了するのは2041~51年になる見通しという。
伝え続ける使命 胸に刻む【記者コラム】
福島第1原発1号機から100メートルの場所でバスを降りると、線量計の数値が跳ね上がった。車内では毎時0・1マイクロシーベルトだった放射線量は、毎時70マイクロシーベルトを示した。隣を歩く福島県内の地元記者によると、4年前の取材時より格段に放射線量は減ったという。それでも50メートルほど先を見やると、作業員が防護服を身にまとっている。自分の身軽さに不安を覚えた。
草で覆われたパチンコ店の看板にさびた車。バスから眺めた福島第1原発が立地する大熊町は、13年前から時が止まっているように見えた。これでも不要な建物は壊され、土地の除染が進んでいるという。初めて被災地を目の当たりにした私にとって、13年たっても生々しく残る大震災の爪痕は想像以上に深かった。
講座中、参加者の1人が「汚染水漏出のニュースは自社の紙面では小さな扱いだった」と発言し、はっとさせられた。講座を通して出会った被災者にとって、今後の人生を左右する死活問題。「報道はどう向きあっているのか」を突きつけられた気がした。
目に見える形での復興は進む。だが放射能は目に見えず、被災者や消費者の不安は消えない。「こんなこと言っちゃいけないかもしれないけど原発事故が風化してほしい」。ある被災者の言葉には「全てなかったことになればいいのに」という複雑な思いすらにじむ。被災者にとって忘れたい過去もあるだろう。報道の難しさも実感した。
50年後、東日本大震災の記憶を鮮明に語れる人がどれだけ残っているだろうか。小学生だった発生当時の記憶は大まかにしか残っていない。「知ったような口を利くな」と言われるかもしれない。それでも被災地を訪れ思う。二度と悲惨な事故を起こさないための教訓を、震災を経験しなかった人々に記事として届け、伝えるのが私たちの使命だ。
【講座の参加媒体】
岩手日報、河北新報、秋田魁新報、福島民報、福島民友、下野新聞、新潟日報、北陸中日新聞、信濃毎日新聞、中日新聞、静岡新聞、京都新聞、神戸新聞、山陰中央新報、中国新聞、西日本新聞、熊本日日新聞、南日本新聞、琉球新報、日本農業新聞
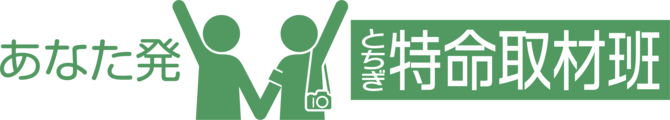
 ポストする
ポストする