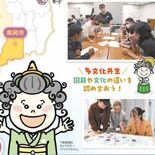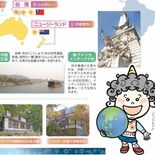地域特有の気候や地形をうまく利用した料理は人々の生活を支えてきました。今回は、長く受け継がれてきた郷土料理を紹介します。
2月ごろになると家庭の食卓や給食で目にする「しもつかれ」は、本県を代表する郷土料理の一つです。正月に食べた塩引き鮭の頭や、節分で残った福豆などの残り物が材料で、栄養も豊富。先人の知恵が生きます。
本県が生産量全国1位を誇るかんぴょうを使った料理も親しまれてきました。かんぴょうにさまざまな具材を加えた「五目飯」や、かんぴょうを卵でとじた汁物「かんぴょうの卵とじ」など多彩です。
海から遠いため、比較的腐りにくい「モロ」「サガンボ」と呼ばれるサメ類を食べる文化も本県特有です。川の流域ではアユやマスなどの川魚が重宝されました。
コメの収穫量が少ない日光や那須地域の山間部では、かつてはヒエや麦を主食としていました。日光市の栗山地区では、特別な日にうるち米で「ばんだい餅」を作りました。二毛作が盛んな県南部ではコメの裏作として麦が生産され、うどんやまんじゅうがよく食べられました。
民俗学を研究する県立博物館学芸部長の篠崎茂雄さんは「郷土料理から地域や文化の特徴が分かるので、目を向けてみてほしい」と魅力を伝えます。

 ポストする
ポストする