下野新聞「あなた発 とちぎの特命取材班」(あなとち)などの合同アンケートで、原発活用を容認する回答が2023年より減ったのは、能登半島地震の発生で原発事故への懸念が強まった影響があったとみられる。今後の原子力政策をどうするべきか-。原発立地県の声を紹介する。
「福島(原発の事故は)は、能登半島でも起きたかもしれない。志賀原発(石川県志賀町)の避難訓練も形式的だけだったことが、今回の地震で良くわかった」。石川県七尾市の自営業の女性(63)はこう指摘し、アンケートで「積極的に廃炉とし、脱原発を急ぐべきだ」を選んだ。
能登半島では、同県珠洲(すず)市での原発立地計画が03年に凍結された。「もし建設されていたら」と懸念する声も多数あった。
東京電力柏崎刈羽原発がある日本海側の新潟県。同原発30キロ圏の外に位置する南魚沼市の男性公務員(64)は「立地自治体には恩恵があるかもしれないが、他の自治体は(事故時に)危険にさらされ、自分の県で使わない電力を首都圏に供給する矛盾を感じる」と脱原発を望んだ。
全国最多の原発がある福井県敦賀市の男性会社員(55)は、「運転期間の延長も必要で、(新しい技術を導入した)革新型軽水炉に着手しないとエネルギー不足に陥る」と指摘。「増設や建て替えなど積極的に原発を推進」を選択した。
立地地域の現実を代弁する声もあった。四国電力伊方原発が近い、愛媛県八幡浜市の学校事務職員の女性(75)は「基数を減らしながら原発活用すべきだ」と回答。「現実として、原発の関連企業への就職や、補助金で周囲の自治体は成り立っている。原発を失えば、地域に仕事もなくなる」と漏らした。
一方、九州電力川内原発がある鹿児島県薩摩川内市の女性(75)は「積極的に廃炉とし、脱原発を急ぐべきだ」と考える。「稼働を続ければ、使用済み核燃料は増え続ける。その再処理の体制がいまだに整っていない」と、滞る国の核燃料サイクル政策を批判した。
◇ ◇
アンケートは以下の20紙が参加しました。 岩手日報、河北新報、秋田魁新報、福島民報、福島民友新聞、下野新聞、新潟日報、北陸中日新聞、福井新聞、信濃毎日新聞、静岡新聞、中日新聞、京都新聞、愛媛新聞、高知新聞、西日本新聞、熊本日日新聞、南日本新聞、琉球新報、日本農業新聞
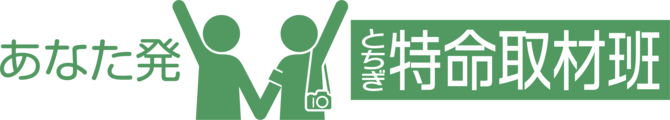
 ポストする
ポストする















