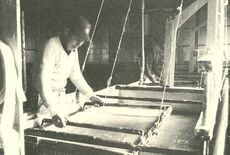古くから農業が主要産業だった野木町だが、明治以降、北関東の近代産業を支えたのが渡良瀬遊水地近くにある旧下野煉化製造会社煉瓦(れんが)窯(野木町煉瓦窯)だ。
同社は1888年設立。翌89年に西窯(関東大震災で全壊)、90年に現在も町煉瓦窯として残る東窯が完成した。ドイツ人技師フリードリヒ・ホフマンが考案したホフマン窯を採用。16区画に分かれた窯で順次、予熱や焼成、冷却、窯出しなどの工程を行うことで大量生産を可能とした。
この地に窯を設けた理由として、町教委生涯学習課の宮田(みやた)あゆみ文化振興指導員は「れんがの原料となる良質な粘土や川砂が、近くの渡良瀬遊水地や思川で採取できたことや、水運による輸送がしやすかったことがある」と説明する。
日本の近代化の流れに乗り、同社の煉瓦窯は順調に生産を拡大していった。最盛期の1918年ごろには年間約600万本の赤れんがを生産。北関東を中心に建築資材として重宝されるなど、インフラ整備に貢献した。
戦後になると産業構造の変化もあり、生産量は次第に減少。71年にれんが製造が終了し、80年以上にわたる歴史に幕を下ろした。ただ製造終了後も煉瓦窯は町のシンボル的存在として残り続け、79年に国重要文化財となり、2007年には近代化産業遺産群に選定された。
煉瓦窯は06年、町へ譲渡された。町は11年から4年間にわたる大規模な修復工事を実施。16年には隣接地に町交流センター「野木ホフマン館」も整備され、煉瓦窯関連の資料などを展示するほか、町内の観光拠点としても親しまれている。

 ポストする
ポストする