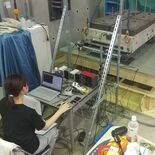那須塩原市西那須野中では、同校の地域学校協働本部やPTAが主体となって年に1回、防災学習の場を設けている。中学3年間で自助・共助・協働を段階的に学び、自然災害が発生した時に自分の命や家族を守り、地域社会の一員として自ら考えて主体的に行動できるようになることを目標としている。
防災学習は2021年、当時のPTA役員だった斉藤誠之(さいとうさとし)さんと遠藤優美(えんどうゆみ)さんらが中心となって企画。斉藤さんと遠藤さんの子どもたちは卒業したものの、地域学校協働本部の推進員として活動している。
遠藤さんは、西那須野地区は災害が比較的少ないとした上で「子どもたちが進学や就職で地元を離れ、災害に巻き込まれる可能性もある。自分や家族、仲間と生き抜くすべを学んでほしい」と強調する。
今年は11月初旬、市総務課危機管理室や那須地区消防組合、市建設業協会、地元の防災士ら60人以上が協力。学校全体にさまざまな体験ブースを設け、防災の知識やスキルを身につけた。
段階的な学び
1年生は防災の基礎となる「自助」を学ぶため、発災時の行動をまとめる「マイ・タイムライン」を作成。防災士のアドバイスを受け、実際のハザードマップを確かめながら、自宅や学校周辺で起こりうる災害のリスクを学び、避難所の位置や家族との連絡手段の確認、情報収集方法などを検討した。
2年生になると、1年次に習った自助に加えて周囲の人たちと助け合う「共助」について理解を深める。校庭には8つのブースが並び、消防署員や看護師らプロの指導を受けて応急手当や心肺蘇生法、土のう作りなどを体験。段ボールを使った簡易トイレをいかに早く頑丈に作れるか競い合ったり、毛布を使った担架で友人を運んだりと、遊びの要素を交えながら役立つ知識とスキルを学んだ。

3年生は総まとめとして、避難所運営ゲーム(HUG)に挑戦。生徒は4、5人のグループに分かれて同校の構内地図を参考に乳幼児がいる家族や高齢者、外国人ツアー客らさまざまな事情のある避難者をどのように受け入れるかを議論。途中、支援物資の調整や避難者からのクレームなどのトラブルにも対応するため、頭を抱えながらゲームを進めた。
実際に避難所で使われる資材も用意され、生徒たちは実際に段ボールベッドに寝転んだり、簡易トイレに腰掛けたりして使い心地を確認。東野航祐(あずまのこうすけ)さん(15)は「3年間の学習を通じて防災の知識が高まった。ボランティア活動にも参加してみたい」と前向きだ。

地域と学校で
生徒たちが生き生きと訓練に臨む姿を見て、斉藤さんは「地域の皆さんが学校の活動に携わってくれ、中学生も地域のボランティア活動に参加できる仕組みを整えた。子どもたちを地域と学校で育てていきたい」と目を細める。
相馬幸男(そうまゆきお)校長は「今年の3年生は防災学習を3年間積み上げた最初の学年。ここで得た知識やスキルを卒業後もさまざまな場所で生かしてほしい」と話した。

 ポストする
ポストする