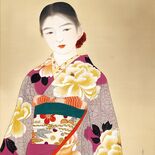海のない本県に、太古の海の痕跡が残っている。
佐野市北部の葛生地区(旧葛生町)には、約2億6千万年前に生成されたとされる石灰岩地帯が広がる。サンゴや貝類などが堆積してできた石灰岩は、栃木市と接する山間部にかけて南北約30キロの弓なりに分布。葛生化石館の奥村(おくむら)よほ子(こ)学芸員(44)は「大きくカーブした形が馬のひづめに似ていることから『馬蹄(ばてい)形』と呼ばれている」と説明する。
葛生町誌によると、初めて同地区で石灰岩層が見つかったのは安土桃山時代の1596年。石灰岩を焼いて作られた石灰は、肥料や藍染めの補助剤として活用されたほか、江戸城の修復や日光東照宮の造営に利用された。
明治に入ると石灰は都市建設に必要な国産セメントの原料として需要が高まり、東京への輸送を円滑にするため、葛生-佐野間で安蘇馬車鉄道が開通。現在の東武佐野線の前身となった。
大正時代には、石灰岩層の中間から高品質な石灰石「ドロマイト」の大鉱床も発見された。県石灰工業協同組合の資料によると、全国埋蔵量の約8割を占める。現在もセメントなどの工業原料や建築資材として採掘され、人々の生活を支えている。
明治期から始まったとされる、石灰岩の洞窟や地層での化石発掘も盛んだ。1968年には、数十万年前に生息したニッポンサイの全身骨格が見つかるなど、歴史的な発見も多い。
奥村さんは「葛生の石灰岩は産業に欠かせない素材だけでなく、当時の歴史を保存するタイムカプセルのような役割も担っている」と、その価値を語った。

 ポストする
ポストする