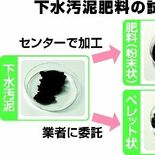真岡を盛り上げるフルーツはイチゴだけじゃない-。「いちご王国栃木の首都もおか」を掲げる市にあって、不動産会社が畑違いのパッションフルーツ栽培に丹精し、30代の若者たちはバナナ栽培に懸ける。イチゴのシーズンが終わった今から楽しめる南国のフルーツで新たな主役の座を狙う挑戦を紹介する。
人の背丈を優に超えて生い茂る緑の葉と1本の木に100本以上実が付いている様は、とても市内の農業の景色とは思えない。
「まずは多くの人に食べてもらいたい」。西高間木(こうまぎ)のバナナ農園「ラフファーム」。台町出身の豊田恵介(とよだけいすけ)さん(35)が、取り組み3年目にして実った成果をいとおしそうに眺めた。
農家からハウス16アールを借り、大阪府で過ごした大学時代のバイト仲間で親友の長谷川優斗(はせがわゆうと)さん(35)と21年4月から栽培を始めた。もともと2人とも会社員。新型コロナウイルス禍で社会が激変する中、漠然と抱いていた「いつか2人で起業したい」という思いを実現するタイミングが来た気がした。
需要が安定しているのに流通品種が少なく、ほとんどが輸入。関心があった農業の中からバナナにチャンスを見いだした。地元の友人佐藤浩映(さとうひろあき)さん(35)も誘い、3人で奮闘している。
始める前に長谷川さんが愛知県の農家で栽培技術を学んだが、現実は厳しかった。1年目はウオーターカーテンと呼ばれる保温技術やストーブをたく努力もむなしく、冬の寒さで50株が全滅した。子株が残ったことだけが絶望感を和らげ、気力を保った。
22年4月に再び定植し、教訓を生かした。クラウドファンディングで資金調達して暖房設備を整備するなど温度管理を徹底し、今季の収穫にこぎ着けた。
「軌道に乗った感じはないです」と豊田さんは苦笑いする。同じ環境、栽培法でも収量、品質、収穫のサイクルが安定せず、試行錯誤の経験から学ぶ毎日だ。
扱っている「サンジャク」と呼ばれる系統の品種は、国内ではほとんど流通がない。香り高く、味は濃厚。子どもや、バナナが苦手な人が笑顔で食べてくれる、そんなおいしさへの評判と自信が苦労の中での何よりの支えだ。市のふるさと納税の返礼品にもなるなど手応えを感じつつある。
ブランド名は、攻めた「とちおとこ」。県、真岡市が全国に誇るイチゴといつか比肩する存在に-。「市に人を呼ぶ観光資源に育てたい。チャレンジしがいがあるんです」と長谷川さんは前を見据える。若者たちの挑戦は始まったばかりだ。
 ポストする
ポストする