ワカメなどの養殖が盛んな志津川湾から約300メートル離れた平地に、震災遺構の「高野(たかの)会館」(南三陸町)が残されている。社会福祉協議会の職員だった佐々木真(ささきしん)さん(51)は震災時、この会館にいた。

あの日、老人クラブの芸能発表会が行われていた。突然の大きな揺れで、会場はパニック状態に。津波襲来の情報を入手し、高齢者を上階へ避難誘導しているさなか、「バキバキバキ」と建物が壊れる音がした。
高さ約20メートルの屋上に迫るがれき混じりの濁流が間近に迫ってきたが、「恐怖心を通り越して別世界に来た感覚」だった。近くの病院の患者がベッドごと流されていくのが見えた。「これ以上津波が来たら、皆で手をつないで流されよう」と覚悟したという。

食糧や水分をほぼ摂取できないまま、朝を迎えた。がれきの中、約2時間をかけて小学校まで歩き、救助を要請した。消防隊員が会館に駆けつけ、会館に残っていた300人以上が助かった。
家族とは避難先の小学校で再会した。災害の際は小学校で待ち合わせるよう共有していたという。「いつどこでどんな災害が起こるか分からない。だから備えが一番大切」と訴える。

間もなく12年。町の現状について「ハード面の復興はほぼ終わったと言えるが、やはり昔の町の方が好きだった」とさみしさも感じている。同級生が亡くなったことを考えると、「モヤモヤは晴れない」といい、「本当の意味での復興は来るのだろうか」と、複雑な心境を吐露した。
■ ■
「失ってから大切だったと気付いた景色がある」
そう語るのは、沿岸部の歌津地区にあった自宅を流された大沼(おおぬま)ほのかさん(24)。小学6年で被災し、北海道に2年間避難した。地元へ戻ったのは中学3年の時。のどかでゆったりとしていた古里は、もうなかった。

宮城県農業大学校に進学後、研修で内陸部の入谷地区を訪れた。津波の被害を受けず、のどかな時間が流れる田園地帯。もう戻ってくることのない、かつての歌津地区が思い起こされた。そして、気づいた。
「こうした環境を守ってきたのは農家。そんな人たちの助けになり、好きだった景色を取り戻したい」。2019年、入谷地区で新規就農をした。
「震災で1番変わったと思うのは人」と感じている。閉鎖的な傾向があった町が世界中からボランティアを受け入れたことで、新しいことにも理解を示すようになったという。

現在は、周りの人の助けを借りながら、果樹栽培を中心とした「大沼農園」を1人で営む。地元食材を使ったクレープの移動販売も手がけている。
将来の目標は、農園直営のカフェの開設。「訪れた人が素の自分に戻れるような空間をつくり、誰もが心の古里と思える町にしたい」との意欲を示した。

取材を終え、全体討議も行われた

「わがこと」考える大切さ 下野新聞記者
記者3年目の私(28)にとって、被災地や被災者の取材は初めてだった。東日本大震災は報道や資料で知るばかりで、「わがこと」として考えることはなかった。
今回、言葉を詰まらせながら苦しい胸の内を明かしてくれた被災者の姿に接し、熱いものがこみ上げてきた。
大沼さんと佐々木さんはそれぞれ、「当時のことを話すと、津波が町を襲う光景や音が戻ってくる」「亡くなった友を思うとすごく辛い」と心に傷を負っている。それでも取材に応じてくれたのは、「これ以上犠牲者が出てほしくない」(佐々木さん)という強い願いからだった。
残念ながら、震災の記憶や教訓の風化は進んでいるのではないだろうか。「皆、心の底では『自分は大丈夫だろう』と思っている」という佐々木さんの言葉が頭から離れない。
災害はいつどこで起こるか分からない。私たちも当事者意識を持たなければいけないと、遅ればせながら実感した。
大沼さんは記者に向けて、「被災地のことをどんどん報道してほしい」とも話していた。責務を果たしていきたい。

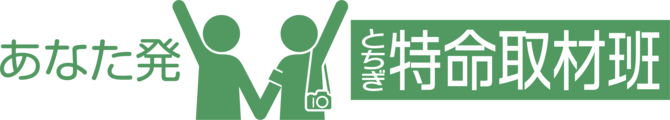
 ポストする
ポストする

















