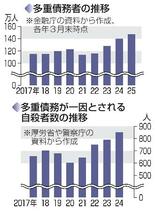「収量を増やすにはどうすればいいですか」。今月上旬、宇都宮市下田原町のビニールハウスで、イチゴのベテラン生産者饗庭孝行(あいばたかゆき)さん(70)は、実習中の郷間隆久(ごうまたかひさ)さん(46)から次々と質問を受けていた。
県は2021年度、全国初の「いちご学科」を県農業大学校に開設した。意欲のある人を県内外から呼び込み、2年間の実践的な授業を通じ技術力のある担い手を育成する。2年次からの実習を指導するのがベテラン農家で、学生が就農後も気軽に相談できるよう就農先の近隣から選ばれる。
1期生(6人)の1人、郷間さんは会社員から転身。今春以降週3回、収穫、育苗、ハウスの手入れなど一連の作業を肌で学んできた。「日々、細かな気付きを得られている」。来春、晴れて独り立ちする。
◇ ◇
本県は半世紀以上、生産量日本一を誇る。一方、高齢化などで離農が進みイチゴの生産者数は20年時点で1863戸。10年前より2割弱も減った。産地の担い手確保が課題となっている。
就農後も含め手厚い支援が鍵を握るとして県が進めるのが、情報発信から研修、就農、定着までを一貫して支援する体制づくりだ。
実効性を高めるため、本年度、イチゴ作りに関心のある人たちの事情に合わせたオーダーメード型の支援に乗り出した。
志望者1人に対し、県や県農業振興公社、JAなどによるサポートチームをつくり、課題解決策を提案する。「相談者に歩み寄りながらサポートする新たな取り組みだ」。県経営技術課の担当者は力を込める。
入り口の一つとなるのが、10月に県が開設したウェブサイト「tochino(トチノ)」。農業の始め方から、各市町の支援制度、最大の問題とされる農地取得まで幅広く紹介する。
◇ ◇
高齢化による生産者減に悩むのは福岡県も同じだ。
同県では、栽培に必要な技術を学ぶ施設「トレーニングファーム」の設置が進む。西日本鉄道とJA全農ふくれんが設立した会社や県内5JAがそれぞれ開設した。
さらに同県は本年度、新事業を打ち出した。熟練生産者を匠(たくみ)として認定。新規就農者に、眼鏡型のウェブ端末「スマートグラス」をかけてもらい、離れた場所からでも匠がリアルタイムで助言できるようにする。
独自の方法で担い手育成に取り組む両県。就農を希望する人をいかに呼び込み、育てていくか、共通の課題に向き合っている。

 ポストする
ポストする