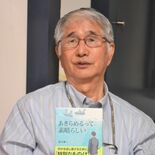戦後日本を代表するジャーナリストの一人で鹿沼市出身のノンフィクション作家柳田邦男(やなぎだくにお)さん(88)=東京都在住=は、米寿を迎えてなお新作の執筆や月刊誌への寄稿、講演と精力的に活動を続ける。宇都宮市で3日開会するマスコミ倫理懇談会全国協議会の第66回全国大会に合わせ、本社客員論説委員を務める柳田さんにデジタル社会に新聞が果たす役割や報道の在り方、将来像などについて語ってもらった。
■取材記者の職業倫理
デジタル化が取材上の便利さをもたらす半面、負の要素も考える必要がある。新聞・テレビを含め取材し表現して伝えていく記者は、職業倫理として何に留意しなければならないか。
一つは、記者はリサーチャーであるということ。調査し、掘り下げ、背景にある問題は何なのかを調べる。現場に早く駆け付けて第一報を伝えるだけでなく、継続的に問題を追いかけていく責務がある。新聞記者、テレビ記者の第一原則だと思う。当たり前だと思うかもしれないが、意外に現実はそうでもない。裏取りの夜討ち朝駆けで話を聞けば、それでやったと終わりがちになる。
次に問題の背景に何が隠れているのか、それを分析する力、推測する力が求められる。これも難しいが、鉄道事故や航空機事故の分析を事例研究として一度でも学ぶとずいぶん違う。
■「なぜ」を問い詰める
例えば1月2日に羽田空港で発生した航空機同士の衝突事故は、なぜ海上保安庁機は滑走路上に許可無く入ったのか、なぜ進入着陸寸前だった日本航空機は気付かなかったのか。「なぜ、なぜ」と問い詰めていく。専門的に「なぜなぜ分析法」というのがある。過去の事例を取り上げて、専門家を招いて分析法を練習する。その積み上げの中から、付け焼き刃ではない非常に深掘りした良い記事が生まれてくる。
■読者の期待に応える
読者が期待しているものは何か。20年ほど前から東京都内の中央紙の夕刊に、ヒューマンドラマのような物語が1面によく掲載される。人の生死や人生の浮き沈みの話は、同時代を生きる人間にとって極めて関心の高い話だ。そのことから言えるのは、朝刊1面トップに座りのいい政治記事を掲げる月並みな編集ではなく、紙面構成はもっともっと大胆に変わっていい。
論説にしても、時には学者や面白い小説家らの評論記事を1面トップにしてもいい。八方ふさがりの状況だからと言って、八方が満足するような記事を狙っても意味がない。個性的な内容で「そういう見方もあるのか」「そうだよなあ」と拍手を送りたくなるような記事が1面トップに出てくることが、これから新聞が生きていく上でものすごく大事なことだと思う。

柳田さんは近著「この国の危機管理 失敗の本質」(毎日新聞出版)の中で、「新聞がこれからも生きていくには、役割をしっかり果たしていかないといけない。(略)情報環境が変わっても、報道の使命は変わらないと考えている」と訴える。その使命や新聞の今後について詳しく語ってもらった。
■調査・分析能力
新聞ジャーナリズムにとってスクープは非常に重要だ。では、何がスクープか。
(構成 論説委員・茂木信幸)
残り:約 1057文字/全文:2451文字
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

 ポストする
ポストする