「近所にオオキンケイギクが咲いている。特定外来生物で、これから種が飛んでくる。取り上げてほしい」と、下野新聞「あなた発 とちぎ特命取材班(あなとち)」へ読者から投書があった。オオキンケイギクは5~7月、道端や河川敷などで黄色い花を咲かせる。繁殖力が強く、在来種の生態系を脅かすため、栃木県は「生息域を広げないよう、庭などで見つけたら残さず刈り取って処分してほしい」と呼びかけている。
国立環境研究所のデータベースによると、オオキンケイギクはキク科の多年草で草丈は30~70センチほど。北米原産で、1880年代に観賞や緑化用として国内に持ち込まれた後、全国各地で自生するようになった。
荒れ地でも生育し、在来種から生息環境を奪い取るほど生命力が強いとされる。在来種の減少や消失を招くとして、環境省は2006年、特定外来生物に指定した。販売はもちろん、栽培したり移植したりすることも禁止されている。
県立博物館によると、本県では主に平野部の河川敷や道路脇、空き地などに自生する。
さくら市の鬼怒川河川敷では、市指定天然記念物のチョウ「シルビアシジミ」の食草の生態を脅かす恐れがあるとして、自然保護団体が毎年駆除をしている。
同館の担当者は「特定外来生物とは知らず、きれいだからという理由で庭先や河川敷などに植えられているケースがある」と警鐘を鳴らす。県自然環境課によると、花を切って持ち帰るのも、種の移動に該当するため禁止されている。
庭先などで見つけたらどうすればいいか。同館の担当者は「放置すれば種が広がる“拠点”となりかねない。早めに抜き取り、ビニール袋に入れて処分してほしい」と話している。
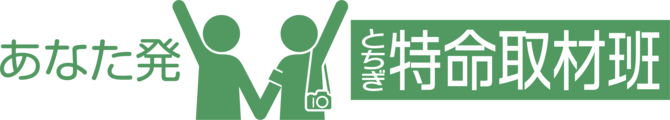
 ポストする
ポストする



















