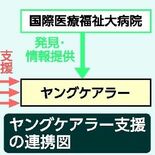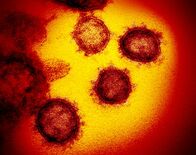本県の救急医療の課題解決に向け、県が2024年度、新たな検討会を立ち上げる方針を固めたことが、3日までに分かった。医療関係者ら有識者がメンバーとなる予定。本県は公的医療機関数が全国ワーストで、各県立病院に感染症や一般救急の部門がなく、高度救命救急センターが関東で唯一ない。新型コロナウイルス感染症の拡大で露呈した救急医療の脆弱(ぜいじゃく)性などを踏まえ、改善策を議論するとみられる。
救急医療体制の整備については、昨年12月の県議会一般質問で岩佐景一郎(いわさけいいちろう)保健福祉部長が「県内の救急患者を確実に受け入れられる体制を構築する必要がある。医療機関などと協議しながら必要な施策を検討したい」と述べていた。
県内の救急医療を巡っては、課題が山積している。21年に県内12の消防本部・局で119番を受けてから救急車が傷病者を医療機関に搬送するまでの平均時間は、前年比1・5分延びて44・1分となり、県が記録を遡(さかのぼ)れる1998年以降で最長となった。全国平均の42・8分より1・3分長く、98年比で17・5分延びた。
高齢化の進展やコロナ禍で受け入れ病院の確保に時間を要したことが影響したとみられ、受け入れまでに4回以上要請するなど搬送先の決定に時間がかかる「救急搬送困難事案」も多発。このため県は次期県保健医療計画(2024〜29年度)の素案で、重症者の搬送平均時間の短縮や受け入れ困難件数の割合の引き下げなどを目標に盛り込んだ。
一方、ことし4月から医師の時間外労働の上限が原則、年間960時間に制限されるため、救急医療体制に影響が出ないような支援体制も求められている。県は医師確保の取り組みを進めるとともに、医療機関での働き方改革の相談支援体制の充実も図る方針。
 ポストする
ポストする