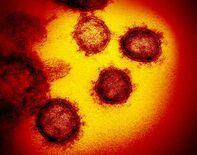性的少数者らのカップルの関係を公的に証明する「パートナーシップ宣誓制度」を栃木県が導入してから今月で1年がたった。9日までに計14組のカップルが申請し、宣誓を行った。このほか独自に制度を設ける県内9市町でも計12組が宣誓している。先行県に比べ周知度が低いといった課題もあることから、県は啓発活動を強化している。
同制度では性的少数者らがパートナー関係を誓う書類などを提出すると、宣誓カードを交付する。カードを提示すると公営住宅に共に入居できるほか、県内17カ所の中核病院などで親族と同等の面会などが可能になる。住宅ローンや生命保険でも加入先によっては夫婦同様の扱いを受けられる。
県内では鹿沼、栃木、日光、野木の4市町が県に先行して制度を始め、佐野市は県と同じ2022年9月、大田原市と那須塩原市は同10月、小山市と那須烏山市は23年4月から導入した。市町別の宣誓数は鹿沼が4組、日光と小山が各3組、栃木が2組。他の5市町は現時点ではない。
先行する茨城県では制度開始から1年で33組、群馬県では20組ほどが宣誓した。本県の現状について県人権施策推進室の担当者は「制度が知れ渡っていない可能性がある。宣誓しやすい環境をつくるために、性の多様性への県民の理解を促進する必要がある」と話す。
啓発事業として県は今月、県庁昭和館を性の多様性を象徴するレインボーカラーにライトアップ。初の試みで、一人でも多くの人に理解を深めてもらおうと企画した。
昨年度まで県職員や医療・福祉関係者向けに開いていた研修会は、対象を企業経営者や従業員に広げて実施。人材会社などの担当者が「多様性を組織の力に変えるために現場で必要なこと」などをテーマに講義し、動画配信する。
県内の事業所に啓発ポスター掲示も呼びかけ、制度への賛同の輪を広げ、宣誓カップルへの民間サービスの拡充にもつなげていく。
 ポストする
ポストする