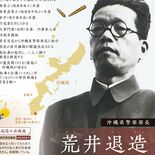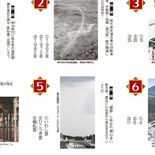人びとの暮らしから生まれ、古くから地域に伝わっている慣習や技術は、大切な財産。ユネスコ無形文化遺産にもなっているお祭りや技を紹介するよ。
那須烏山市内で7月21~23日に開催された今年の「山あげ祭」には、約6万5千人が訪れました。「山」とは、網代状に竹を組んだ枠に特産の烏山和紙を貼り、そこに山水を描いた「はりか山」のことです。若衆たちが人力で立ち上げ、それを舞台背景として、地元の人たちが常磐津に合わせて歌舞伎を演じます。全国でも珍しい移動式の野外劇です。2016年、「烏山の山あげ行事」は国連教育科学文化機関(ユネスコ)無形文化遺産になりました。
豪華で緻密な彫刻が施された屋台が競う「鹿沼今宮神社祭の屋台行事」も、ユネスコ無形文化遺産です。鹿沼市の今宮神社で10月に行われる例祭には、江戸時代に造られたものを含め二十数台の彫刻屋台が奉納されます。彫刻屋台は市街地を練り歩き、“ぶっつけ”といわれるお囃子の競演をします。すごい迫力です。
栃木県最初のユネスコの無形文化遺産は、「結城紬」(2010年)でした。小山市から下野市付近、茨城県の結城市一帯は、古くから養蚕が盛んで、その副産物として紬が織られるようになりました。真綿から糸をつむぎ、柄に合わせて綿糸でくくり、地機で織るすべての工程が手作業。熟練の職人技が必要です。
県立博物館の篠崎茂雄学芸部長は「どれも庶民の生活から生まれ、地域で継承してきた貴重なもの」と重要性を話します。

 ポストする
ポストする