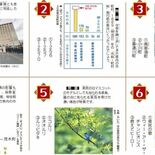那須野が原博物館によると、自動車が日本に輸入されたのは明治時代末。栃木県では1910(明治43)年ごろ、日光の金谷ホテルと日光ホテルが外国人観光客を乗せたのが初めてといわれています。
県の統計に自動車が登場するのは12(大正元)年度。ほとんどが営業用で、家庭用は一般的ではありませんでした。
「県土木史(50年史)」には、14~18(大正3~7)年にヨーロッパなどで起きた第1次世界大戦で好景気になったことや、23(大正12)年の関東大震災で鉄道が大きな被害を受けたことで、道路整備を求める声が大きくなったと書いてあります。でも、日本も関わった第2次世界大戦などの影響で計画はなかなか進みませんでした。
45(昭和20)年の終戦時、県内で改良が済んでいない道は1900キロ以上あり、戦災から立ち直ることなどを目的に、整備が始まりました。65(昭和40)年には県内の自動車の数は10万台を突破しました。
72(昭和47)年には東北自動車道の岩槻(埼玉県)-宇都宮間が開通。県内初の高速道路です。砂利道だった道路の整備も進み、75(昭和50)年には県道の8割が舗装道路になりました。
栃木県にも「ハイウエー時代」がやって来ました。その後も、日足トンネルや尾頭トンネルなどが次々と開通しました。

 ポストする
ポストする