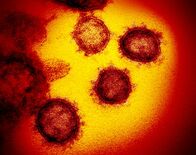突然のことだった。事務所での作業中。目の前にいた男の両手が体に触れた。引き寄せられそうになり、われに返った。
「何してるんですか」。声を出すと、さっと手が離れた。問いただしても悪びれず、ちゃかしたようなにやけ顔が脳裏に焼き付いた。
県央在住の30代女性は昨年、勤務中に当時の上司から性暴力被害を受けた。その日から眠れず、食事も喉を通らない。男に背格好が似た人を見ると体が凍り付いた。働くこともできなくなった。間もなく、不安神経症と診断された。
本人の意思に反した性的な言葉や行動は暴力でしかない。「女性を下に見ているから起きる。人権意識の低さが根底にある」。行き着いたのはそうした思いだった。「女性も男性も同等の立場にある。誰もが自分事として考えてほしい」
◆ ◆
憲法は個人の尊重と法の下の平等を規定し、男女平等をうたう。国も女性に対する暴力を重大な人権侵害としている。しかし現実には性暴力が後を絶たない。
県内では2022年度、専門窓口に1206件の相談があり、この5年間で5倍に増えた。京都産業大現代社会学部の伊藤公雄(いとうきみお)教授は、性暴力の背景の一つを支配欲と指摘。「一部の男性にとって、女性を支配することは自分が男であることの証明になる」とみる。
とちぎ男女共同参画センター(パルティ)で家庭内暴力(DV)などの相談に応じる担当者は、「『男は仕事、女は家庭』といった男女の固定的な役割意識が、今も社会に根強く残っている」と問題視する。
◆ ◆
「被害は誰にでも起きうるし、遠い出来事でもない」。上司から性暴力被害に遭った女性はそう話す。「そんなことくらいで」。体を触られたことをそう言う人がいた。被害を公的機関に訴える中で「勇気があるね」と言われたことも。
「基本的人権について授業で習っても、生活に浸透していない。私たちは人権について考えることもないまま、運良く生活できているだけ」と語気を強める。
国は男女共同参画基本計画で、女性への暴力根絶について「克服すべき重大な課題で、国の責務」と明記。意識改革などが欠かせないとして重視する。
ジェンダーギャップ(男女格差)などをテーマに6月下旬、日光市で先進7カ国(G7)男女共同参画・女性活躍担当相会合が開かれる。関係者は世界的な会議に期待をのぞかせる。「G7を契機に県民全体の意識を変えたい」
◇ ◇
憲法が施行され、3日で76年を迎える。移り変わる社会情勢の下、日常の中で憲法が保障する権利が脅かされる事態が起きている。私たちにとって憲法とは。県内の現場から当事者の思いを通じて見つめ直す。
 ポストする
ポストする