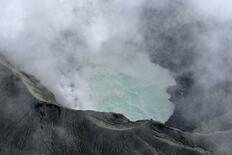「次男が通う中学校で給食の牛乳を飲まない生徒が多く、余った牛乳は捨てているらしい。もったいない」。こんな意見が広島市安佐南区の自営業男性(42)から中国新聞編集局に届いた。市は4月、食品ロス削減推進条例を施行する。学校給食での対策はどうなっているのだろうか。
「捨てるくらいなら、飲まない子の牛乳は最初から頼まなければいいのに」。男性は不思議がる。次男(14)によると、30人のクラスで全く飲まれなかった牛乳が毎日10パック以上残り、中身をバケツに捨てているという。
市内の複数の小中学校で事情を聴いた。ある中学校の教頭は「うちは教員が職員室に持ち帰ってシンクに流している。本当にもったいない」と申し訳なさそうに言う。別の中学校教諭も「苦手だから飲まないという理由では注文を止められない。嫌いでも飲もう、と声をかけて生徒が学校に来なくなってもいけない。結局、捨てることになる」と頭を抱える。
背景に摂取基準
なぜ、苦手な生徒の分まで注文するのか。市教委によると、現在の給食費の範囲内で、国の学校給食摂取基準を満たすカルシウム量を摂取するには、牛乳が不可欠という。牛乳を出さないのは病気やアレルギーの診断書などがある場合だけ。「好き嫌いで提供をやめるのは、バランスの良い食事を提供する学校給食の趣旨に沿わない」(健康教育課)と強調する。
一方、市議会は昨年12月、食品ロス削減を目指す条例案を全会一致で可決した。4月1日施行の条例は「市は食品廃棄の実態を調べ、効果的な削減方法を研究する」などと定める。
現在、どれほどの量の牛乳が学校給食で廃棄されているのか。市教委によると、牛乳の残量は計測しておらず、量っているのは副食(おかず)だけという。「おかずは残食量が多かったら味付けや献立の改善を図る余地があるが、牛乳は毎日同じ人が残すので献立の改善につながらない」(同課)のが理由という。
ただ、全国で見ると牛乳の残量を量っている自治体もある。東京都多摩市は市民の陳情をきっかけに市教委が昨秋、学校給食で診断書なしでも個別に牛乳の注文を止めることができる「選択制」にする方針を決めた。2023年度中に実現する予定という。
データ取り議論
同市学校給食センターによると、21年11月に市内の公立学校の配膳室に牛乳専用のはかりを導入。多い学校では1日の廃棄量が20キロを超えると分かった。佐藤彰宏センター長は「具体的なデータを知ることで食品ロス削減に向けた議論が進んだ」と話す。牛乳なしの子どもは水筒でお茶や水を持参。給食費は牛乳分だけ減額するという。
意見を寄せた安佐南区の男性の次男は、給食当番のたびに他の生徒が残した牛乳を捨てるうちに「もったいないというより、早く作業が終わらないかな、面倒くさいな、という気持ちが強くなった」と明かす。
廃棄に慣れるあまり、もったいないという意識が薄れているのであればなお見過ごせない。市教委はまずは実態を把握し、食品ロスを減らす対策につなげてほしい。
(中国新聞)

 ポストする
ポストする