アンケートでは県議会の身近さを「とても感じる」から「全く感じない」まで4段階で尋ねた。20代は回答者250人中、身近に感じない層が77・6%いた。
小山市を拠点にイベント企画などのまちづくりに取り組む一般社団法人「カゼトツチ」の学生スタッフで白鴎大3年諏訪惟人(すわゆいと)さん(21)は「実際の仕事を知らない」と情報不足を指摘する。実生活でも県議会の影響を感じにくいと話す。
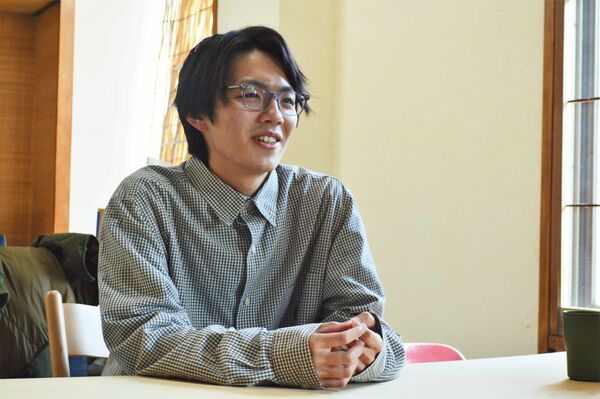
身近に捉えにくいのは「議員」という立場の印象の強さだ。「肩書にびびって話しかけづらいイメージ。小中学校で県議会場を見学するなどして幼い頃からなじみがあれば違うのかもしれない」と想像する。
若者と地域作り事業を手掛ける宇都宮市のNPO法人とちぎユースサポーターズネットワークの職員中山裕貴(なかやまひろき)さん(25)は、人となりが見えてこないと話す。「身内の誰々が議員をやっているぐらいの距離感なら親しみを持てるかな」

“身内”に感じられる情報発信に関し、那須烏山市在住、ウェブデザイナーの女性(22)は、交流サイト(SNS)での発信強化を挙げる。重要とするのは「企画」と「受け手が交流できている感覚」だ。
若者などから質問を募りそれに答える投稿を挙げている県議に着目している。「私の質問を取り上げてくれたことがうれしくて、投稿をチェックするようになった」。質問は地元の話から「人前でうまく話せるようになるには」「政治家にならなかったらどうしていたか」など身近な悩みや話題にも及ぶ。女性は「やりとりから人となりが見えるのが楽しい。結果として議員や政治が身近になった」と説明した。

高齢者の居場所作りなどに取り組む大田原市の一般社団法人「えんがお」の門間大輝(もんまだいき)さん(29)も「政治活動とは別のしかけ」の必要性を説く。
日常の政治活動や支持層と関係なく読書会などを主宰するのも手として「政治と生活の結びつきを意識させるきっかけを作ってほしい」と求めた。

 ポストする
ポストする

















