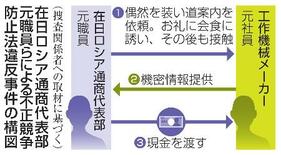4月9日投開票の県議選を前に、10〜30代の若年層の声を集める「選挙どうする?」。日々の困り事から政治参加について考えるワークショップに取り組む市民グループ「こまとど」のメンバーに、市民の声を政治に届けるアイデアや、地方議会、行政の印象について語ってもらった。

ワークショップでは、政治を考えるきっかけ作りとして身近な困り事を集めた=12日午後、宇都宮市
■困り事を政治へ
-政治参加の手段として、なぜ「困り事」にフォーカスしたのか。
さおちゃん(37、公務員) 「私たちの声が社会を変えるという実感を持つ」ことがテーマ。政治を身近に感じてもらうために、普段困っていることを集めることにした。
ぐっさん(37、公務員) 個人の努力では解決できないことに取り組むのが政治だけど、身近な困り事と政治が結びついていない。本質的に政治に関心がない人はいないと思うけど、解決策が分からず関心がどんどん下がってしまう。
なおちゃん(36、会社員) 世代間や住んでいる地域でも困り事は違う。お互いがどんなことで困っているかは分かっていないよね。昔はよく軒先に集まって井戸端会議をしていた。でも共働きが多くなるなど生活スタイルも変わって世代的に忙しくて、ちょっとした情報交換をするタイミングもない。
-ワークショップではどんな困り事が出てきた?
さおちゃん 税金が高い、物価高で家計が厳しいといったお金の話や、キャリアと家庭どちらをとるかという悩みもあった。
ぐっさん 教育に力を入れている自治体に住みたいという人もいた。例えば子どもが安全に使える歩道を整備してとか、自転車マナーを改善してほしいとか。
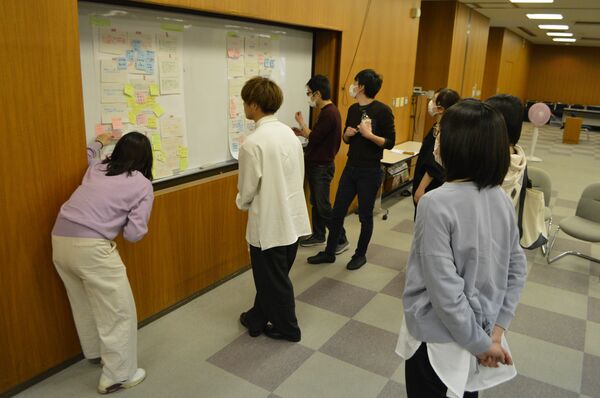
ワークショップでは、政治を考えるきっかけ作りとして身近な困り事を集めた=12日午後、宇都宮市
なおちゃん 子育て支援では出産から小学校入学までは手厚いけどそれ以降もお金は掛かる。共働きしてる層も余裕があるわけじゃない。所得制限なしに塾代を補助する自治体もあるもあって良いなと思う。。
ぐっさん 行政が行っているのは再分配だと思っている。市民から税金を集めていくらを高齢者支援に充てるか、どう子育て施策を充実させるか、とか。どのようにお金を使うかというプロセスにもっとみんなが参加できると、より政治に興味が湧くと思う。
■政治を話す場作りたい
-政治への印象が変わったタイミングは?
さおちゃん 子どもが生まれてからNPO主催の勉強会に参加するようになって。こんなにも社会のために動いている人がいるんだ、自分たちが動かないと変わらないと気付いた。

さおちゃん(中央
ふくちゃん(36、会社員) 学生時代から外国人へのヘイト問題に関心があったけど、私一人が行動しても何も変わらないと無力感があった。その一方で「じゃあ誰に頼ればいいの?」と政治を意識するようになった。どうせ変わらないとは思っているけど、自分だけで解決できないなら社会ごと変えないといけない。
-政治や行政との距離感を縮めるには?
ぐっさん 行政だけでできる問題は大体カバーしている。今ある課題について知ってもらい、どうやれば解決できるか一緒に行動する協力者を増やしたい。
市町では首長が地域を回る懇談会をしているが一部の人しか来ないし、県議会は情報公開度ランキングも高くないけど話題になっていない。「情報公開しないのはおかしい」と危機感を感じる県民が増えて内容をチェックしないと、政治の質も上がらない。
市町では首長が地域を回る懇談会をしているが一部の人しか来ないし、県議会は情報公開度ランキングも高くないけど話題になっていない。「情報公開しないのはおかしい」と危機感を感じる県民が増えて内容をチェックしないと、政治の質も上がらない。

ぐっさん(左)
なおちゃん いろいろな意見を持つことは悪いことじゃない。食事会とかオンラインとか、さまざまな形で政治について話す機会を続けていくのは大事。こういった場が増えれば議員にとって見逃せない存在になるし、ぜひ一緒に参加してほしい。。
■問題解決のキーマン
-市民の困り事をどう政治へ届けていくのか?
ぐっさん 集まった声を書面にまとめて市議会の各会派にお渡ししたい。みんなが何に困っているのか、議員とコミュニケーションを取っていくことから政治への道筋を作りたい。
ふくちゃん でも若い世代は人口が少ないから、議員は若い人たちのことを本音では気にしていないんじゃないかな?
さおちゃん 選挙に行っていない人がみんな投票したら、政権が代わるとも言われている。若い人の票はいらないのかも。
ぐっさん 政治家は自分の支持層にばかりマーケティングをする。ある政党は支持層だった農家や企業の経営者にアピールしていたけど、今は農家も大企業も減った。共働きも増えているけど、社会の変化にアジャストできていない。
さらにSNSが発達したから、マイノリティーの集団がつながれる。
さらにSNSが発達したから、マイノリティーの集団がつながれる。

なおちゃん(中央)、ふくちゃん(右)
-政治に期待する役割とは。
なおちゃん 自分たちで解決できない、アイデアが出てこない問題を解決するには、政治や行政の力が必要だよね。。
ふくちゃん でも選挙は人選びで、問題が解決されるイメージがない。
ぐっさん 行政は大工のような存在と言われたことがある。国民の思いを聞いて作らないと、トイレだけ多くてお風呂がないといびつな家になってしまう。
その例えで言うと、政治家は周囲の支持を得ながら問題解決に取り組む役割だから、「こういう家に住むぞ!」と方針を示す大家族の大黒柱だと思う。住みたい家は人によって違うけどみんなが意見を言わないから、住みやすい社会に発展しない。
その例えで言うと、政治家は周囲の支持を得ながら問題解決に取り組む役割だから、「こういう家に住むぞ!」と方針を示す大家族の大黒柱だと思う。住みたい家は人によって違うけどみんなが意見を言わないから、住みやすい社会に発展しない。
ふくちゃん 満足していないけど問題はないし、ギリギリ住める家だからね。
ぐっさん また国、県、市町村の役割は分かりにくい。
-若い世代に政治に関心を持ってもらうには?
なおちゃん 子どものうちから選挙や政治が問題解決の手段だと知ってほしい。。
ぐっさん 海外では子どもの頃から実際の政党を学び、施策を議論する機会がある。日本でもそういった場が必要。有権者教育は学校任せになっているし、選挙が近付いてからでは遅い。普段の学校活動に絡めてほしい。
さおちゃん でも社会が変わるのを待っているのは難しい。興味を持っている人たちが立ち上がらなければいけないね。

日常の困り事から政治参加について考えるこまとどメンバー

 ポストする
ポストする