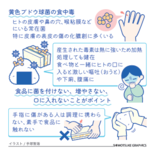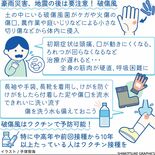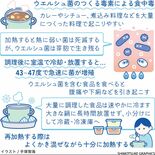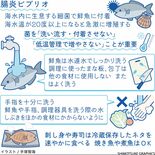百日ぜきは、百日ぜき菌の感染で起こります。コンコンと激しくせき込んだ後、笛を吹くようなヒューという音で息を吸う、この苦しい咳嗽(がいそう)発作が日に何度も繰り返されます。この激しいせきが3カ月も続くことがあり、強い感染力で小児を中心に患者が発生します。
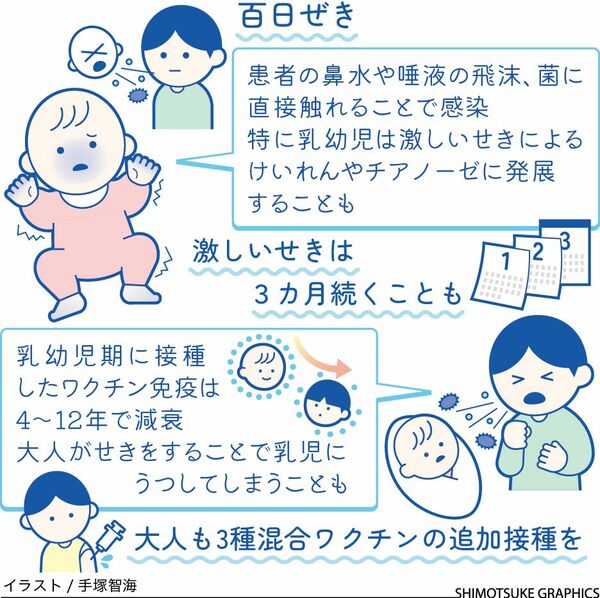
残り:約 839文字/全文:982文字
この記事は「下野新聞デジタル」の
スタンダードプラン会員・愛読者(併読)プラン会員・フル(単独)プラン会員
のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

 ポストする
ポストする