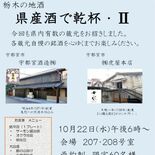栃木県産初のジャパニーズウイスキーが10月下旬、西堀酒造(小山市)日光街道小山蒸溜所から発売される。ブランド名は「哲-TETSU-」。日本酒蔵としてウイスキー事業に参入した思い、その独自性、世界をも見据えた将来展望を3回に分けて追う。
◇ ◇

西堀酒造の6代目蔵元、西堀哲也さん
ウイスキー事業を主導するのは西堀哲也(にしぼり・てつや)専務(35)だ。創業153年の西堀酒造6代目蔵元として2016年、蔵に戻ってきた。その頃を「ウイスキー事業に参入するなんて思ってもみなかった」と振り返る。しかし20年に襲った新型コロナウイルス禍は、飲食店での会食を控えることを感染予防の要としたため、酒類の消費量が激減した。西堀酒造も例外ではなかった。
それまでも国内の日本酒需要は30年以上にわたり減少の一途をたどり、今後の人口減少も見据えると、国内市場に明るい展望を描きづらかった。日本酒の輸出が増加しているといっても、海外での流通は日本料理店などに限られ、世界に出回るワインやウイスキーの流通量に比べると、桁違いに少なかった。
残り:約 1554文字/全文:2053文字
この記事は「下野新聞デジタル」の
スタンダードプラン会員・愛読者(併読)プラン会員・フル(単独)プラン会員
のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

 ポストする
ポストする