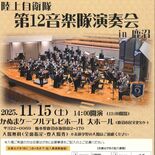鹿沼秋まつりの“顔”である彫刻屋台は、まつり最終日の12日も26台が市街地に集結する。屋台蔵を唯一持たない末広町では毎年、秋まつり前に若衆たちが組み立て作業を行う。一体どんな作業が行われているのか。9月下旬、現場を取材した。
◇ ◇
今宮神社氏子町所有の彫刻屋台は27台あり、市の施設や各町の屋台蔵に保管されている。かつてはどの町も屋台を解体して保管していたが、祭りのたびに組み立てる負担感もあり、平成に入ると蔵を建ててそのまま収蔵する町が増えた。末広町は「用地や予算の都合」(町関係者)で、唯一保管場所を持たない。
今年の組み立ては28日午前8時から町内で行われた。10~50代の若衆約50人が集まり、100以上ある木製の部品を軽トラックで作業場に持ち込むところから始まった。同町の屋台は1883(明治16)年制作。改修費などを含めた総額は数千万円にも上る“町の宝”だ。「壊すなよ」「両手で運べ」。若衆たちが声を掛け合いながら慎重にブルーシート上に並べる。

末広町で行われた屋台の組み立て作業
残り:約 1491文字/全文:1970文字
この記事は「下野新聞デジタル」の
スタンダードプラン会員・愛読者(併読)プラン会員・フル(単独)プラン会員
のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
 ポストする
ポストする