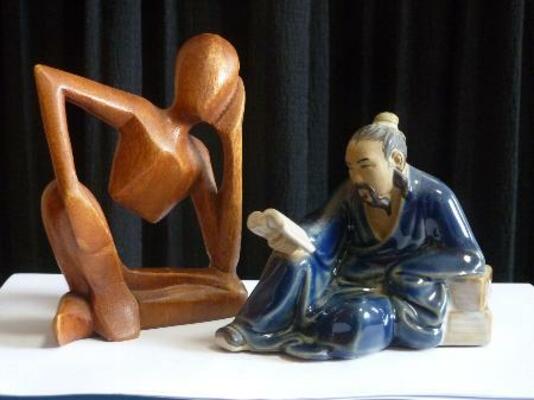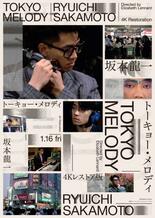先月ご案内した通り、この連載は今回を以て終了する。理由は幾つかあるが、ネタ切れのためではない。いずれ書こうと考えていた本や音楽を、黙って冥土へ送るのはもったいないので、せめて名前だけでも挙げさせてもらおうと思う。
その前に、少しだけ過去3年間を振り返ってみる。開始前の予定では、各回1冊ずつ取り上げ、分量は2000字ぐらいと思っていたのだが、どんどん膨れあがって最後は7000字を超えた。1回当たりの冊数も大幅に増えた。見通しが甘かったと言えばそれまでだが、作家がなぜその音楽を選び、どういう意図でこの場面に書き入れたのかと考えるのが、思っていた以上に面白く、また奥深いものだったからである。文が長くなりすぎれば飽きられるとは承知しながら、筆まかせに書き連ねた。多少は厚みも出たと思いたい。
全体の半分より少し多くが外国文学だった。国内作家の場合も含め、作中から取り出した音楽はほとんど外国ダネである。日本の音楽を素材にした作品に十分手が回らなかったのが悔やまれる。とはいえ、候補がなかったわけではない。近松門左衛門の浄瑠璃『堀川波鼓』と夢野久作の怪奇小説『あやかしの鼓』を取り合わせて鼓の世界を覗いてみようとか、谷崎潤一郎の『春琴抄』はどうだろうかとか考えたことがある。文楽三味線なら有吉佐和子の『一の糸』、新内節なら川口松太郎の『鶴八鶴次郎』……と見ていけば、素材には事欠かない。
歌謡曲も気になっていた。庄司薫の『赤頭巾ちゃん気をつけて』には、ピンキーとキラーズの『恋の季節』や水前寺清子の『どうどうどっこの唄』の名が見える。朱川湊人の『かたみ歌』では、レコード店のスピーカーから西田佐知子の『アカシアの雨がやむとき』が聞こえ、トランジスタラジオから布施明の『シクラメンのかほり』やザ・タイガースの『モナリザの微笑』が流れた。言い古された「歌は世につれ、世は歌につれ」を持ち出すまでもなく、ヒット曲は生まれた時代と切り離すことができない。年代の絞り方ひとつでいろんなことが書けたはずである。
井伏鱒二の短編『軍歌「戦友」』は特にやっておきたかった。学徒動員された世代がそろそろ定年を迎える時期の話である。泊まりがけの宴会が行われているときに客室から金が盗まれた。『戦友』(ここは御国を何百里)を延々と合唱しているとき泥棒に入られたらしい。駆けつけた警察官の話によれば、宴会泥棒が忍び込むのは、皆が軍歌を歌っている時が多いとのことである。酒もまわって宴たけなわ。『戦友』は14番まであるから、なおさら仕事がしやすい。
アイ・ジョージの録音ではこの曲、8分余りかかっている。14番まで通したあと1番に返って終わる、その見事な歌いっぷりを含めて紹介するつもりだったが、残念ながら機会を逸した。
井伏より30歳以上若い野坂昭如に『軍歌』という短篇がある。主人公は学校回りの楽団(普段は『カッコーワルツ』や『クシコスの郵便馬車』を演奏)で経営面を担当する男である。既にエレキギターがもてはやされている時代だが、職員室で軍歌の話をしたところ大いに盛り上がり、ついには教師その他を集めて『軍歌合唱会』を公会堂で開くに至る。書き切れないほど沢山の軍歌が出てくるが、前述の『戦友』に関して主人公の妻が「ここはお国を三百里とかいうのそうでしょ。アイ・ジョージ唄ってたわ」と言うのに目がとまった。アイ・ジョージといえば『硝子のジョニー』、あるいは『ラ・マラゲーニャ』などのラテン音楽が思い浮かぶが、こうしてみると『戦友』も代表曲に含めなければいけないと認識を新たにした。
戦中派が軍歌にノスタルジーを感じていたころ、一方では歌声喫茶がブームになったり、勤労者対象の芸術鑑賞団体が多くの会員を集めたりした。『軍歌』の主人公は元々、歌声喫茶のマネージャー兼合唱リーダーだった。また、懐古趣味と一緒にはできないにしても、アイ・ジョージの『戦友』は大阪労音のコンサートでライブ録音されている。歌声喫茶を舞台にした小説に曽野綾子の『ぜったい多数』があり、山崎豊子は『仮装集団』で鑑賞団体の内幕を描いた。
村田喜代子の『エリザベスの友達』では、中学校や女子校の合唱部、市民コーラスグループが高齢者施設の慰問に訪れる。中学生は童謡の『たきび』、女子高生は『アヴェ・マリア』(シューベルトのであろうか)を歌ったが、市民グループはもっと入居者の年齢や経験に密着した選曲である。植民地育ちのご老人たちには懐かしいだろうという発想で『満州娘』『アリラン』『支那の夜』が選ばれ、また、ここでも『戦友』が歌われた。大晦日には『蛍の光』。しかし、今も歌われている1番、2番に続いて3番、4番に入ると「ひとつにつくせ くにのため」「台湾のはても 樺太も やしまのうちの まもりなり」と帝国主義的色彩が強くなる。『エリザベスの友達』を全体としてみれば、ユーモアと暖かみのある小説だと思うが、戦時歌謡が青春の歌だった世代があることも同時に考えさせられた。
戦争と音楽についてもう少し続ける。まず竹山道雄の『ビルマの竪琴』。ビルマ(現在のミャンマー)に送られた日本軍の中に、戦線においても合唱を楽しんでいる部隊があった。賛美歌、ドイツやイタリアの名曲、『荒城の月』『朧月夜』『パリの空の下』など数あるレパートリーの中で、お得意は「埴生の宿」だった。現地の竪琴をまねて作った楽器で伴奏した。この曲はイングランド民謡の「ホーム・スイート・ホーム」が原曲である。敵性歌曲とは思わなかったのだろうか。『庭の千草』も歌った。こちらはアイルランド民謡『ラスト・ローズ・オブ・サマー』である。
合唱に夢中になっているとき、遠くにイギリス軍の姿が感じられた。危険を感じた彼らが取った行動は、すぐ攻撃に出ることではなく、歌い続けることだった。敵の存在に気付いていないふりをして時間を稼ぎ、その間に戦いの準備をするのである。『庭の千草』『埴生の宿』が終わるのと同時に態勢が整った。いざ突撃、と思った瞬間に森の中から歌声が聞こえてきた。イギリス兵が『ホーム・スイート・ホーム』と『ラスト・ローズ・オブ・サマー』を歌っていた。スコットランド民謡を原曲とする『故郷の空』はやがて、双方から歌声が起こった。いつの間にか両軍の兵士は手を握り合い、一緒に歌い出していた。日本側は知らなかったが、実はその3日前、停戦になっていたのである。
この場面に真実味があるかどうかは別にしても、明治以降、外国曲(特にイギリス系のもの)に日本語の詞が付けられ、ほとんど日本の歌のように親しまれてきた歴史を踏まえていることは確かである。郷静子の『れくいえむ』にも、『故郷の空』をめぐる逸話がある。主人公・節子の兄は出征前、この曲を口笛で吹くのが好きだった。戦後早くに駐留してきた米兵の口笛で<スコットランド民謡>を耳にした彼女が、特攻隊で出撃した兄を思って錯乱し、「お兄ちゃん!」と叫んで倒れるシーンが最後に用意されている。曲名は書かれていないが、当然『故郷の空』と考えてよいと思う。
話は変わるが、文芸作品に最も縁の深い作曲家は誰だろう。まずはモーァルトに指を折りたい。例を挙げよう。三浦哲郎の『モーツァルト荘』は館内にモーツァルトの音楽ばかりが流れるペンションである。宮本輝の書簡体小説『錦繍』に出てくる喫茶店<モーツァルト>では、モーツァルトのレコード以外かからない。遠藤周作に『ピアノ協奏曲二十一番』があり、鮎川哲也の推理小説に『モーツァルトの子守歌』がある。中山可穂の『ケッヘル』に登場する会員制旅行代理店は、顧客の会員番号をモーツァルト作品の成立順を示す「ケッヘル番号」から取っている。歌劇『ドン・ジョヴァンニ』に関係するものとしては村上春樹『騎士団長殺し』、島田雅彦『佳人の奇遇』、ブリジッド・ブローフィ『雪の舞踏会』(本連載の第33回に既出)がなど挙げられる。
ベートーヴェンやバッハの出てくる小説も少なくないが、ヴィヴァルディにかかわる本が意外に多く、いま4冊手元にある。キューバ出身の作家アレッホ・カルペンティエールの『バロック協奏曲』では、時空を超えてヴィヴァルディ、ヘンデル、ドメニコ・スカルラッティが一堂に会して大合奏を繰り広げる。クリスティアーネ・マルティーニの『猫探偵カルーソー』はヴィヴァルディ秘蔵の宝をめぐって展開し、大島真寿美の『ピエタ』は慈善院でヴィヴァルディに音楽を習っていた少女たちの物語。山口椿の『黄昏のヴェネツィア』には作曲家若き日の悦楽が描かれる。
では、音楽を作中に書き込むことの多かった作家は誰だろう。すぐ思い浮かぶのは五木寛之である。この連載ではタンゴとの絡みで『夜明けのタンゴ』(第24回)と『遙かなるカミニト』(第25回)を取り上げるにとどまったが、『海を見ていたジョニー』『さらばモスクワ愚連隊』などのジャズ、『暗いはしけ』のファドを忘れていたわけではない。『戒厳令の夜』にチリのシンガー・ソングライター、ビクトル・ハラの名前が出てくることも頭の中から離れなかった。五木には本とCDをセットにした6巻の『五木寛之クラシック小説集』があり、歌謡曲の業界ものも手がけている。<音楽を書く作家>の代表格であることは間違いない。
小池真理子の小説からは『リリー・マルレーン』(第21回)と『ソナチネ』(第22回)を選んだが、それ以外にも、『死に向かうアダージョ』や『無伴奏』といった作品がある。前者には<アルビノーニのアダージョ>として知られる有名な楽曲(本当の作曲者は別人のようだ)が現れ、「かつての自分をモデルに使いながら」書いた小説だと著者が明かす後者のタイトルは、仙台に実在した名曲喫茶の店名である。ちなみに佐伯一麦の著書『読むクラシック』によると、彼も高校時代、この喫茶店の常連だったという。
クラシック、ラテン、シャンソンなどに比べ、ジャズを描いた小説をあまり取り上げていなかったことに気付いた。日本の作家に限っても村上春樹、五木寛之、倉橋由美子、中上健次、大江健三郎、筒井康隆、奥泉光、栗本薫をはじめ、実に多くの人たちが書いている。その中でも、石原慎太郎の『ファンキー・ジャンプ』は強く印象に残る作品だった。
ジャズにかかわる小説には、ミュージシャンの生き方を描くもの、ジャズ喫茶やライブハウスを舞台にするものなど様々あるが、『ファンキー・ジャンプ』は即興演奏そのものに入り込み、奏者の想念とも交差させて描写する。文章そのものがジャズ的だ。短いフレーズを束ね、改行を重ねてどんどん加速する。
「敏夫は持ち上げた指をキイに置いた。/瞬間、横の糸へ縦が編み込まれた。/キイが掌の先で転げる。/ジェリーがそれに乗る。触るようなスティック。/ベースが滑り込む。ピアノの間にベースが沈む。/ピアノは、丸く、浮き上がり、/こぼれ、こぼれ、/はずんですべる。/ジェリーが底でスティックを流しながらそれを支える。/小さな、HOP、&、TRIP、小さく。/おお、なんて軽い――/TOHM TOHM ZUHM/RIPAH・RAHPAH・PAHHH――」
「これは 君のくれた薬だぜ/君が言っていた時が 今来たんじゃないか/俺はこの瞬間を俺のものにしている/いや 俺は脱けていってこの中にいる/俺はこのブロー自身になった/俺はもうシャンギーじゃない/俺はバップだ!」
<シャンギー>がよく分からない。<ジャンキー>のことかもしれない。それはさておき、この文章のリズム感は素晴らしい。なお、『ファンキー・ジャンプ』に関しては、平岡正明の『ビーバップと日本文学』というエッセイに詳しい分析がある。
クラシック関係では、落合恵子の『バーバラが歌っている』を取り上げないうちに最終回が来てしまったのを残念に思う。女性が人生で直面する諸問題に目を向けたこの小説の最終章で、バーブラ・ストライサンドが専門外のクラシックを歌ったアルバム『クラシカル・バーブラ』が大きな意味を持つ。主人公の亜弓がいま一番好きなCDである。祖母のフミはそれを聴くと「バーバラさんが歌ってるね」と言う。ドビュッシーの『美しい夕暮れ』、ヴォルフの『語らぬ愛』などに加え、ポピュラー音楽の分野で高名なクラウス・オーガーマンの<I Loved You>も入っている。
亜弓がフミにこんなことを言った。「正統クラシックを自任するひとは、バーブラ・ストライザンドが歌うクラシックに、きっと眉をひそめているかもしれないわ」。フミがその理由を聞くと、亜弓は「クラシックはこんなふうに歌ってはいけないとか、ドイツ語の発音がなってないとか……。つけようと思えばいろんな難癖をつけられるでしょ」と説明した。「でも、バーバラさんは、自分のやり方で、気持ちよさそうに歌っているじゃないの」とフミ。「そこよ、フミさん。自分のやり方で気持ちよくっていうのを認めないひとは結構いるのよ(後略)」。
<自分のやり方で気持ちよく>を認めないのは、音楽ばかりでなく社会一般にあるというのが、言外にありそうだ。いや、むしろそれを言うために『クラシカル・バーブラ』がここに置かれたのだと考えていいかもしれない。フミが<バーブラ>を<バーバラ>と間違えて覚えても、亜弓はそれでいいと思っている。「このうちでは、バーバラさんで通っているんだもの……」。あまり正誤にこだわると息苦しくなる。小説の題名がバーブラではなくバーバラになっているのも、<自分のやり方で気持ちよく>を際立たせるためだと思えば納得がいく。
同じ曲がいくつもの小説に使われることがある。邱永漢の『濁水渓』、黄春明の『海を訪ねる日』、日影丈吉の『応家の人々』には、共通して台湾の古い流行歌『雨夜花』(☆(登の右に郊のツクリ)雨賢作曲)が出てくる。『濁水渓』では「女の美しさと儚さを、雨の夜に風と雨に打たれておちた花に托して歌ったもので、その甘い淡いメロディーは古くから台湾の民衆に親しまれている」と紹介されるが、そのメロディーに日本語の詞をつけて『誉れの軍夫』という曲に仕立てられたことも苦々しく付け加えてある。
在庫はまだいくらでもあって、話し出せばきりがない。しかし、そろそろ筆を擱くときが来たようだ。いずれどこかでこの続きが書ければと思う。(松本泰樹 共同通信記者)
まつもと・やすき 1955年信州生まれ。『クラシカル・バーブラ』は私も昔から愛聴している。今夜、寝る前にまた聴こうか。
 ポストする
ポストする