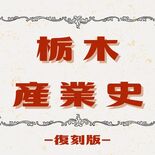2005年に下野新聞紙面で連載した「戦後60年 とちぎ産業史」。第2次世界大戦後、栃木県内の産業や企業はどんな盛衰のドラマを繰り広げたのか-。今年は戦後80年。関係者の証言などを収めた20年前の記事を通して、あらためて戦後の歩みを振り返ります(9月7日まで毎日配信予定)。記事一覧はこちら。
【戦後60年 とちぎ産業史】イチゴ
「グミ」と、さげすまれて呼ばれていたこともあった。
「今の世の中、グミなんか作ることはない。コメと麦を作っていればいいんだ」
グミとは、イチゴのことだった。
一九五六年、二宮町物部地区。同町物井の上野純一氏(74)は二人の友人とともに、同地区にイチゴを導入しようと仲間に働き掛けていた。若手約三十人で組織する農事研究会で導入を勧め、物部農協にも協力を求めた。だが、農協上層部は気乗り薄だった。
「農協にとっては新しい作物。栽培法が分からないということもあり消極的だった」。上野氏は振り返った。
ただ、職員の故大橋司男氏は協力的だった。組合長ら幹部と農家との間を取り持ち、農協としても導入に協力する形を作った。
翌五七年七月上旬、上野氏らは農協からオート三輪を借り、御厨町(現足利市)の栽培農家から「幸玉」の苗を譲り受けた。有志六人が二アールずつ植え付け、五八年春、初めて収穫した。
日本一のイチゴ産地・二宮が産声を上げた。
残り:約 2312文字/全文:2918文字
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
 ポストする
ポストする