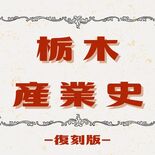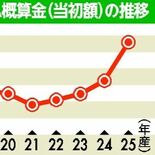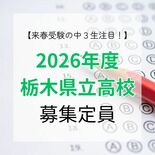2005年に下野新聞紙面で連載した「戦後60年 とちぎ産業史」。第2次世界大戦後、栃木県内の産業や企業はどんな盛衰のドラマを繰り広げたのか-。今年は戦後80年。関係者の証言などを収めた20年前の記事を通して、あらためて戦後の歩みを振り返ります(9月7日まで毎日配信予定)。記事一覧はこちら。
【戦後60年 とちぎ産業史】稲作(下)
かつて不足していたコメが余り始めていた。
一九七〇年、政策のかじが正反対の方向に切られた。六九年の試験実施を経て、減反(生産調整)が始まった。
「余剰米の処理に金が掛かると言われると、国と争う気にはなれなかった」。真岡市の山前農協組合長だった県農協中央会会長の豊田計氏(78)は振り返った。コメ百万トンを廃棄すれば千五百億円の国の資産を失うといわれていた。
六七年、全国の収穫量は前年より二百万トン増え千四百万トンを上回った。この水準が三年続いた。七〇年、政府のコメの在庫量は七百二十万トンに達した。コメ余りは深刻な状況となった。
コメの増産政策を進めた結果だった。四千円台から八千円台へと順調に上昇していった六〇年代の米価が、生産意欲を高め、増産の動きを加速した。本県の収穫量も六九年には四十二万七千トンとなった。さらに高度経済成長による所得増大で、国民の食生活が変化し、コメの消費量は落ち込んでいた。
政府は、奨励金を出して転作や休耕を勧めた。コメの増産に熱心に取り組んでいた高根沢町の野中昭吾氏(78)は戸惑った。「今までコメを作ってきたのに急に野菜を作れと言われてもね。でも国の政策だからどうしようもなかった」
七一年の本県の減反面積は一万九千ヘクタール、翌年は一万七千ヘクタールだった。
増産を目指し六〇年代半ばに急増した開田が、本県ではマイナスに作用したという。「昔からの水田に比べ開田の割合が多いということで、栃木は転作率(水田面積に占める減反面積の割合)が全国でも上位だった」。豊田氏は説明した。
残り:約 2009文字/全文:2862文字
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
 ポストする
ポストする