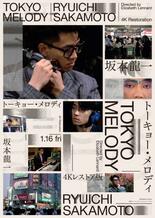東京都中央区明石町の一帯には、明治政府が開設した築地外国人居留地があった。約10ヘクタールの居留地には、各国の公使館などが置かれ、宣教師や医師らが教会や学校を設けた。1901年創設の聖路加病院を原点とする聖路加国際大もその一つ。文明開化の名残がある街を東京メトロ日比谷線築地駅から歩いた。(共同通信・藤原朋子)
大学キャンパス内で目を引くのがトイスラー記念館。欧州の山荘風の建物は33年の建築で宣教師の住居として使われ、現在の地に移築された。
毎週月曜と水曜に見学できる。1階では病院創設者で宣教医師のルドルフ・B・トイスラーの生涯を手紙や写真で紹介。2階には病院付属の高等看護婦学校の初代校長が暮らした部屋があり、病院の発展を伝える展示室として活用されている。
トイスラーは、病院とチャペルの融合を目指した。病院の旧館の聖ルカ礼拝堂は、かつては患者が病棟のバルコニーから礼拝に参加できたという。同大と病院にとり「チャペルは心臓部なのです」と司祭成成鍾さんは話す。ステンドグラス越しに美しい光が差し込む礼拝堂内では祈りをささげる女性の姿も。穏やかな時間が流れていた。
築地場外市場へと足を延ばす。マグロ店の店頭では高価なにぎりずしに人だかりができていた。「フーズネクスト(次は誰の番)?」と日本人店員が観光客に声をかける。商品紹介の看板も英語記載。まるで市場の公用語が英語になったようだ。
卵焼きが看板商品の「つきぢ松露」は創業から100年を超え、本店を場外に構える。中央卸売市場の豊洲移転後、プロの買い出し人が激減したといい、その代わりに外国人観光客の波が押し寄せる。3代目店主斎藤元志郎さんは「時代の流れを受け止めながらも、築地が日本の台所だったことを発信し続けるよ」と威勢良く話した。
【メモ】聖路加国際大の構内にある「聖路加健康ナビスポット るかなび」では、健康や医療に関する蔵書を閲覧できるほか、看護師に有料で健康相談ができる。
 ポストする
ポストする