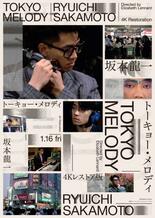◎今週の一推しイベント
【5日(土)】
▽「考土 code―奄美―」(~14日、新宿区・Mikke Gallery、入場無料)
奄美大島(鹿児島県)の豊かな風土を表現した現代アート作品を紹介し、染織の可能性を探求する展覧会が、四谷で開催されている
。
キュレーターは、奄美の伝統織物大島紬の販売で知られる和装専門店「銀座もとじ」社長の泉二啓太さん。アーティスト6組が島に滞在し、自然や文化をフィールドワークして制作した染織作品やインスタレーション28点を展示する。
反物5枚を部屋いっぱいに広げた大型作品「泥中の布(ぎん)」。大島紬の伝統を尊重しつつ、泥染めの色彩の可能性を拡張した試みだ。大島紬の主な染色原料・テーチ木(シャリンバイ)だけでなく、月桃やヒカゲヘゴなどの草木の色で淡く染めた。染織家2人による共作。奄美出身の金井志人さんが糸を5色に染め、民芸運動の柳宗悦の親族である柳晋哉さんが布を織り上げた。
「かつて奄美ではジョウミチャ(上質な泥)の泥田で髪を洗うこともできた。そんな自然豊かな大地に自生するさまざまな草木の存在と向き合っていくことが大切だ」と泉二さんは話す。
故郷の宮古島(沖縄県)を拠点とする新城大地郎さんは、いま国内外で注目のアーティスト。金井さんが奄美の草木で染めたキャンバスに、テーチ木の墨を使って大胆な書を展開した。与那国島(同)と東京を行き来する山崎萌子さんは、手すきの芭蕉紙に泥染めを施し、奄美で撮影した山や湾の写真を印刷。単色の中に美しい自然景観を浮かび上がらせている。
泉二さんは「それぞれの感性で島を見つめ直し、自由な発想で作品に昇華してくれた。島特有の“風土”という財産を最大限に活用し、新たな産業や文化が生まれることを願っている」と語った。
○そのほかのお薦めイベント
【5日(土)】
▽「Otemachi One(大手町ワン)竹あかり―灯りの蕾―」(~8月1日、千代田区)
風情豊かな“竹あかり”を用いたライトアップイベントが、大手町で行われている。
竹あかり演出家池田親生さんが率いる熊本のアート集団「CHIKAKEN(ちかけん)」がプロデュース。駅直結の複合施設「Otemachi One」の緑地空間を中心とする8エリアにそれぞれ異なる竹あかり作品を展示した。
光が醸し出す「和」の雰囲気に合わせて厳選した日本酒や、食事を提供するキッチンカーも出店。日本の伝統と都心の現代性が融合した空間で、夏の夜を楽しみたい。
▽「ザ・リッツ・カールトン東京のメロンパフェ」(~9月中旬、メロンの旬に伴い終了時期に変更あり、港区)
夏の果物メロンをぜいたくに使用したパフェが、赤坂のザ・リッツ・カールトン東京で提供されている。
グラスの中に、新鮮なメロンとメロンゼリー、クランブルを何層も重ね、果実の味わいと食感の楽しさを感じられるように仕上げた。メロンの層の間にココナツ味のパルフェアイスを忍ばせているのも特徴だ。
【8日(火)】
▽「性別を超え、誰もが支え合う『ケアリング・ワークプレイス』とは?~『グレーな』ハラスメントから考える~」(14時、港区立男女平等参画センター リーブラ、オンライン開催、事前予約制、参加費無料)
企業組織でのケアを専門とするコンサルタント中川瑛さんが、法律違反ではないグレーゾーンのパワーハラスメントについて講演する。
職場がギクシャクしてしまうパワハラすれすれの言動を認識し、誰もが働きやすい職場づくりを考える。
【13日(日)】
▽「銭湯のカケラ展」(~21日、目黒区・gallery yururi、入場無料)
銭湯研究の第一人者として知られ、昭和の庶民文化に詳しいエッセイストの町田忍さんが、全国の銭湯から譲り受けた看板やのれんなどの貴重な備品を紹介する展覧会を、自由が丘で開催する。
北海道から沖縄まで約3千800カ所の銭湯を訪ね歩き、おけやブリキ看板、のれんなどを収集。40年近くかけて集めた施設備品から約100点を展示する。「アート作品のようなユニークさや美しさを純粋に楽しんでほしい」
台東区日本堤に1929年に開業した「廿世紀浴場」は、正八角形の白タイルと正方形のブルーの小タイルからなる床や、アール・デコ風の外観が有名だった。2007年廃業後に、クラシックなカランをオーナーからもらい受けたという。
工芸品として価値が高いものも。かつて横浜市にあった銭湯は典型的な宮造りの建物。脱衣所に置いていた看板には、手彫りの松の木などの細工が施されている。
近年はインバウンド(訪日客)をはじめ、海外からも注目されている銭湯。「江戸時代から町人の憩いの場として存在しながら、趣のある銭湯の多くが消えてしまった。その歴史を残したいとの思いで、庶民の生活の“カケラ”としての備品を集め続けている。世界に誇る入浴文化を未来へつなげていきたい」
 ポストする
ポストする