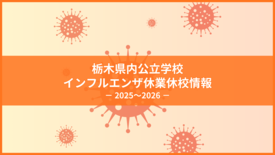「バンカーのないコースでプレーしたい」「あの深いバンカーを埋めてほしい」。バンカーを苦手とするアマチュアゴルファーは実に多い。今回はそのバンカーについて触れてみたい。
由来は、16世紀のスコットランドで石炭貯蔵をするための穴蔵の「ボンカール」。このボンカールが存在する土地をゴルフ場にするべく計画したが、草を生やすにしても何年もかかるし、土を入れるにも時間が必要だ。そこで身近にある砂を入れたのが、バンカーの誕生とされている。
残り:約 887文字/全文:1111文字
この記事は「下野新聞デジタル」の
スタンダードプラン会員・愛読者(併読)プラン会員・フル(単独)プラン会員
のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

 ポストする
ポストする