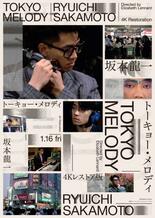太平洋戦争当時、住民の4人に1人が亡くなったという沖縄戦。沖縄に出かけることになり、この機会に少しでも沖縄戦のことを知り、感じることができる場所を訪ねたいと思った。那覇空港に降り立ったのは沖縄慰霊の日の3日前にあたる6月20日。すでに梅雨も明け、灼熱の太陽が照り付けていた。
予定の取材を終え、21日午後から、旧知の詩人で作家の大城貞俊さんの車に乗り込む。まずは糸満市のひめゆりの塔に向かった。
■おさげやおかっぱの少女たち
ひめゆりの塔は、沖縄戦で亡くなった沖縄師範学校女子部(略称「女師」)・沖縄県立第一高等女子学校(同「一高女」)の生徒や教師のための慰霊碑のこと。両校で最も多くの犠牲者を出したガマ(自然の洞窟)のそばに1946年に建てられた(大きな方の「ひめゆりの塔」は1957年建立)。ひめゆりとは、この女師と一高女という二つの学校の愛称。両校は那覇市安里の同じ校舎にあり、校歌も一つ、学校行事も一緒にしていた。13歳から19歳の生徒約1150人が学んでいた。
「火炎瓶を投げた男たちは、このガマに隠れていたんだよ」
大城さんに言われてハッとした。1975年7月、当時の皇太子夫妻の沖縄訪問時に火炎瓶が投げつけられた「ひめゆりの塔事件」は知っていたが、ここに立つまで思い出すことはなかった。思わずガマをのぞき込む。
「これは、ひめゆり学徒隊の引率をした仲宗根政善先生の歌」。大城さんに言われて歌碑を見る。「いはまくら かたくもあらん やすらかに ねむれとぞいのる まなびのともは」。大城さんが小さな声で読み上げる。硬い岩場で亡くなった教え子たちを思って詠んだ歌だろう。哀惜の念が胸に迫る。
ひめゆりの塔の横に立つひめゆり平和祈念資料館に入る。入ってすぐのところにある写真に胸を突かれる。1944年3月に撮影された彼女たち。おさげ髪やおかっぱの少女たちはみな利発そうで、明るい笑顔を見せている。じっと見ていると、どの人も知っている誰かに思えてくる。
女師・一高女は沖縄で最初に設立された女子のための中等教育機関で、離島も含めて県内各地から聡明な少女たちが集まった。自由でのびのびとした校風だったが、軍国主義の中で変わっていく。制服はセーラー服からもんぺになり、体操はダンスから、なぎなたへ。学校主催の最後の米国映画の鑑賞会は1941年、「駅馬車」だった。
戦況が悪化し、1944年には沖縄での戦いが確実な情勢となる。県外への疎開も始まる一方、ひめゆりの校舎の一部が軍に提供される。1945年1月には、地上戦に備えて軍による看護教育を受けるようになる。
1945年3月23日、米軍の沖縄上陸作戦が始まる。すぐに、ひめゆりの生徒の沖縄陸軍病院への動員が決まり、この日の夜、職員18人を含む240人の「ひめゆり学徒隊」は学校から約5キロ離れた南風原の沖縄陸軍病院へ移動する。
そのころはもう、陸軍病院は施設ではなく壕だった。ツルハシや鍬で掘ったトンネルのような壕が40本近くあり、そこで彼女たちは、けがをした兵士たちの看護や世話をした。足の切断手術に付き添い、尿や便の始末をし、過酷な労働に献身した。しかし5月下旬、日本軍は南部に敗走。6月18日夜、陸軍病院は学徒隊に解散命令を下す。「鉄の暴風」と呼ばれるすさまじい戦場に放り出されたのだ。捕虜になってはいけないと教えられていた彼女たちの「死の彷徨」が始まる―。
陸軍病院に動員された240人中136人が亡くなった。ひめゆりでは、その他の地域でも91人が死亡している。沖縄戦でひめゆりの生徒と教師、計227人が亡くなったのだ。
■描かれた死者たちとともに
この資料館ができたのは1989年のこと。元ひめゆり学徒の多くは、長い間、戦争体験を語ろうとはしなかった。重傷を負った友達を戦場に置き去りにしたことや、大切な娘を失った遺族のことを考えたからだろう。生き残って申し訳ないという思い。しかし時間がたつに従い、戦争体験を語り継ぐことこそ鎮魂につながるという気持ちに変わっていったという。残されたひめゆり学徒の証言を大切に、深く受け止めたい。
「平和の礎(いしじ)」に行き、沖縄県平和祈念資料館を見学した後、ひめゆり学徒が働いていた壕の一つ「沖縄陸軍病院 南風原壕群20号」に向かう。大城さんが事前に見学を申し込んでくれていたのだ。ガイドの女性と3人でヘルメットをかぶり、懐中電灯を持って中に入る。
説明によると、長さ約70メートル、高さ1・8メートル、床幅1・8メートルの人工の壕。狭くて暗いので、すぐに息苦しくなる。当時はこれに悪臭が加わった。床の半分ほどに狭いベッドが置かれ、ひめゆり学徒たちはその横を忙しく行き来したのだろう。壁は所々、黒く焦げている。米軍の火炎放射器によるものだ。天井に「姜」の文字が残っている。入院していた朝鮮人兵士が刻んだものではないかとみられているという。
翌6月22日は1人で佐喜眞美術館を訪ねた。普天間基地の敷地に食い込むように立つ美術館で、今は「沖縄戦の図」全14部が展示されていると聞いたからだ。丸木位里さんと丸木俊さんが「原爆の図」全15部を仕上げた後、1980年代になって取り組んだという作品群が見たかった。
「沖縄戦の図」(1984年)に描かれた母娘が首を絞め合う場面について、館長の佐喜眞道夫さんは「生き残った人はその後、地獄の日々だったでしょう」と語る。この絵の右下に描かれた頭蓋骨のうちの二つは、丸木夫妻の自画像だという。「絵の中に自分たちを置く。ここに描かれた死者とともにあるということです」と佐喜眞さん。
「沖縄戦の図」が置かれた部屋の上部には、丸木夫妻が聞き取りをした沖縄の人々の写真が展示されている。2人は沖縄の人たちの話をじっくり聞き、モデルになってもらって、これらの絵を描いたのだという。
日本軍による住民虐殺「久米島の虐殺」を描いた二つの作品(ともに1983年)は、人間の狂気を感じさせる。丸木夫妻はこの作品を「沖縄戦の図」全14部のうち最初に手がけた。
「沖縄戦―きゃん岬」(1986年)には、死者の化身である蝶が舞う。「ひめゆりの塔」(1983年)には、ひめゆり学徒たちの他、火炎瓶を投げた男たち2人も刻まれている。
佐喜眞美術館は1994年開館。「沖縄戦の図」を沖縄に置きたいという丸木夫妻の思いに応えた。米軍と直接交渉して、先祖が残した土地を取り戻したという奇跡のような経緯を佐喜眞さんから聞き、個人でもできることがここまであるのかと驚嘆した。(文・写真は田村文・共同通信編集委員)
 ポストする
ポストする