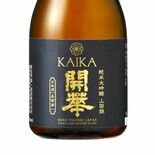2024年12月、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の無形文化遺産に登録された日本酒など日本の「伝統的酒造り」。「伝統」とは何か-。記者は「革新」が絶えず加わり、伴ったからこそ今日まで続き、そして未来につながっていくものだと思う。
24年から「江戸返り」というリブランディングのコンセプトを「革新」に位置付け、新たな日本酒造りに挑んでいる酒蔵が栃木県内にある。銘柄「仙禽(せんきん)」を醸す、せんきん(さくら市馬場)だ。

11代目の薄井一樹(うすいかずき)専務は「日本酒は今が歴史上で最もおいしい、クオリティーが高いと言われている」と語る。一方で各蔵の技術向上により、ある面では科学的になって画一的な酒になり、「銘柄を伏せて味わうと区別が付きにくい」とも評した。
窮地に陥った時期も
せんきんは、安価な酒を量産する昭和の経営を引きずり、窮地に陥った時期がある。2004年、跡を継いだ薄井専務と弟の薄井真人(うすい・まさと)杜氏(とうじ)が試行錯誤を重ねた結果、酸味を生かした酒質は変えず、原料米の地場産化や、古典的な製法への回帰を進めた。
新型コロナウイルス禍で教えられた教訓の一つが「脱成長」だったという。
経済成長だけが暮らしを豊かにするという考え方ではなく、「物質的な豊かさから距離を置いた、経済成長以外の価値である『幸』を見いだすために選んだ手段が『江戸返り』だった」(薄井専務)。スペック(仕様)で日本酒を飲む時代は終わりつつあるとして、「その酒蔵のバックグラウンド、風景、哲学を知ることが大切だと思っている」とも付け加える。

かつては重労働で時間も要した
日本酒造組合中央会の「日本酒の歴史」によると、米、米麹(こうじ)と水で造られる日本酒は約2千年の歴史がある。世に広まり、「並行複発酵」「段仕込み」「寒仕込み」といった、現代とほぼ同じスタイルの製造法が確立したのは江戸時代中期(18世紀ごろ)とされる。ただ、当時行われていたのは「山卸」という櫂(かい)で米をすりつぶす「生酛(きもと)造り」。日本酒の酒母(酛)を造る際、雑菌の繁殖を抑える乳酸菌を蔵内の空気から取り入れる手法で、重労働で時間も要していた。
明治以降、日本酒造りの現場にも、人工的に作られた乳酸菌を使う速醸酛の製造法が入ってきた。速醸酛は酒質が安定し、手間もかからない。効率的に醸造でき、増える日本酒需要に対応できることから一挙に広がり、製造法の主流になった。そこからさらに糖などさまざまな添加物が開発され、作業の機械化、コンピューター化が進んだのが、現代の日本酒造りだ。
酒の原料米も、雑味の少ない心白が大きくなるよう品種改良された酒造好適米(酒米)を使うことが基本となっている。
こうした“当たり前”を見詰め直すとともに、積み重ねてきた技術力を生かし、江戸期の酒造りの原点に戻って「せんきん」のアイデンティティーを打ち出す-。それが「江戸返り」を掲げた今回の取り組みだ。 具体的な事例の一つは、原料米に関わる農業だ。
薄井専務は、化学肥料や農薬を使った農法は「曲がり角に来ている」とし、有機農法による原料米の確保を掲げた。ただ、農家に有機農法を依頼しても、手間暇がかかるだけに賛同を得にくい。そこで23年には有機農法を行う農地所有適格法人「なりはひ」を自ら立ち上げた。地元全体で有機農法を広げる「オーガニックタウン」づくりをけん引していく考えだ。


原料米品種として、品種改良のない江戸時代の在来種「亀の尾」の原原種にもこだわった。亀の尾の原原種作りは9年前に開始。農業生物資源ジーンバンクから入手した数粒を年々増やし、23年に原料米に使えるよう登録。原料面から江戸返りの要件を整えてきた。
設備面でも江戸期再現
また、醸造蔵の設備面でも江戸期の再現を進めている。現代では管理しやすいホーロー製タンクでもろみの発酵管理を行うのが一般的だが、木桶(おけ)を増やし、道具類も木製を導入した。せんきんは、28年には創業222年を迎える。2が並ぶ縁起のいい年を目指し「全てタンクを木桶に切り替える」という。

全量を「生酛造り」に
そして肝心の製造法だ。日本酒は米、米麹以外の原材料の表示義務はなく、さまざまな酵素剤など添加物が使われているのが現実だ。せんきんの江戸返りでは添加物を一切使わず、全商品を「生酛造り」に切り替えた。しかも糖をアルコールに分解する酵母も醸造蔵内に棲(す)む「蔵付き酵母」で醸し、せんきんならではの味わいにした。
24年酒造年度には江戸返り商品として亀の尾原原種で醸した「仙禽 クラシック」をはじめ「仙禽 レトロ」「仙禽 モダン」を出した。評価も高く、販売も好調という。

「AI(人工知能)だって一定水準までおいしい日本酒を造れると思います。しかしその先の数ミリ単位の違いは、人の感情とか気持ちがより込められた日本酒の方がおいしいと感じるはず」と薄井専務。「江戸返りの日本酒で生まれる“いい景色”を未来につなげていきたい」と意気込む。

最後に薄井専務はこんな話も紹介してくれた。同じさくら市内には、F1などレーシングカーにパワートレインなどを供給しているホンダ・レーシングが開発拠点「HRC Sakura」を構えている。この幹部らが蔵を訪れた際、レーシングカーはエンジニアによるネジ1本の締め方の微妙な違いでも走行性能に影響するという話を出し、同じものづくりの立場から蔵人の感性を大切にするせんきんの「江戸返り」の姿勢に共感してくれたという。
せんきんの「江戸返り」という「革新」に注目していきたい。(伊藤一之)

 ポストする
ポストする