場所は堅魚(かつお)市内の割烹(かっぽう)居酒屋だ。麻理亜(まりあ)自身がこの店を選んだのではなく、半ば強引に連れてこられたのだ。
麻理亜が高知空港に到着したのは三時間前の午後三時のことだった。バスなどを乗り継いで堅魚市に向かおうとしたところ、搭乗口から出たところでおじさん二人が待ち受けていた。しかもご丁寧に『歓迎! 紺野(こんの)麻理亜さん』と書かれた画用紙まで持っているではないか。彼らは堅魚市の職員らしく、麻理亜を迎えにきてくれたようだった。公用車に乗せられ、桂浜のあたりを観光がてら走ったのち、堅魚市まで連れてきてくれた。そしてこの店に入ったのだ。
「あのう、どうして夕ご飯までご馳走(ちそう)してくれるんですか?」
麻理亜が率直な疑問を口にすると、おじさん二人が顔を見合わせた。若い方が床山(とこやま)といい、年配の方が赤羽(あかばね)という名前だった。奨吾(しょうご)がウーロン茶を一口飲んで説明した。彼らは仕事中なのでアルコールは口にしていない。
「いや、あれなんですよ、あれ。……ええと、あなたは記念すべき百人目の移住体験者なんです。なので我々もお祝いしなきゃならないんです」
麻理亜は子供の頃に遊園地に行ったときのことを思い出した。麻理亜たち一行の次に入った家族の頭上でくす玉が割れ、盛大なお祝いが始まったことがあった。あれみたいなのものか。
「遊園地で十万人目のご来園者、みたいなやつ?」
「そうです。そんな感じです」と奨吾が答える。「だから遠慮なさらずに。ここはすべて私どもの奢(おご)りですので。ガンガンお食べください」
「それでは遠慮なく」
カツオのタタキを食べる。塩が振ってあり、スライスしたニンニクと一緒に口に運ぶ。ガツンと来るニンニクの香りに負けないほど、カツオそのものに旨味(うまみ)が満ちている。これまでに食べたカツオの中でナンバーワンだ。
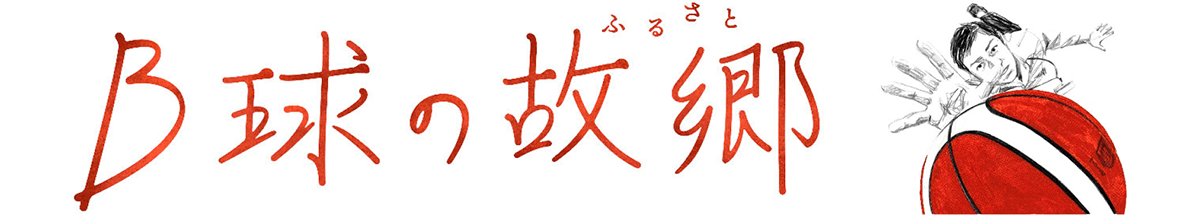
 ポストする
ポストする


















