「まずはこれを見てくれ」
奨吾(しょうご)は手帳のメモを床山(とこやま)に見せた。四つの課題が並んでいる。
「これを一つずつ、クリアしていくしかない。ちなみにアリーナ以外はまったく目途(めど)がついていない」
「うわ、こいつはえらいですね」
床山が体をのけぞらせるように天を仰いだ。奨吾は真顔で言った。
「俺とお前はこの件の専従としたい。もし今後、公務に支障が出るようなことがあったら、そのときはほかの課員に仕事を割り振る予定だ。とにかく二カ月間やってみようじゃないか」
「でもどこから手をつけてえいかわかりませんね」
課題は山積みだ。できれば一緒に汗水流して動いてくれる人材が欲しかった。もし高知クロシオンズの承継がうまくいった場合、その事務局で働いてくれる人間が必要不可欠だ。奨吾たちは表立って事務局に入ることができない。
「協力者が欲しいと思ってな。実は午前中も手当たり次第当たってみたんだが、承知してくれる人はいなかったよ」
市の体育協会や観光協会の関係者、退職した教員など、実務を引き受けてくれそうな人間に打診してみたものの、すべて断られてしまっていた。バスケのチームなんて作ってどうするのさ。返ってきた反応はどれも冷淡なものだった。NBAでは日本人選手も活躍するようになり、先月のパリ・オリンピックもバスケットボールは男女ともに盛り上がったが、その熱は堅魚(かつお)市までは伝わってきていないようだ。
「床山、セルビアにコネあるか?」
奨吾は唐突に訊(き)いた。床山は目をパチクリさせながら答える。
「まあ、ないことないですけんど」
週末は自宅でバスケの試合やBリーグ関連のニュースを漁(あさ)ったりと、バスケの知識を蓄えた。その中でアメリカ以外の強国に目を向けた。ドイツやスペインと並んで、セルビアも常にFIBAランキングの上位にいることを知ったのだ。
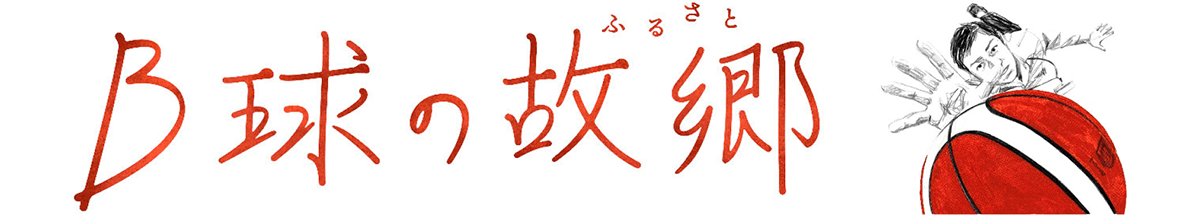
 ポストする
ポストする


















