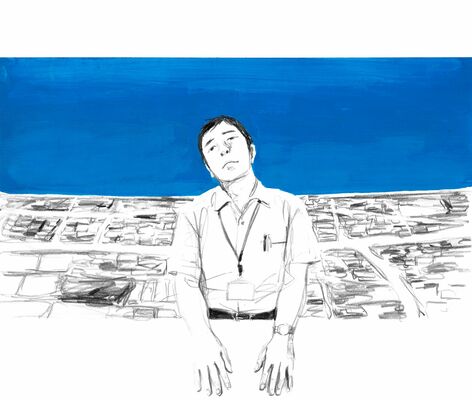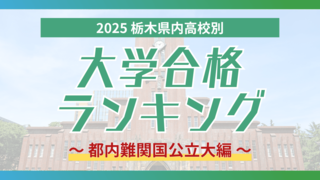さしたる収穫のない会議だった。赤羽奨吾(あかばねしょうご)は手元に置いてある資料を引き寄せ、見るともなしに眺めた。『堅魚(かつお)市地域再生プロジェクト』というタイトルが銘打たれている。一応、奨吾は会議の座長を任されていた。
「やっぱりふるさと納税あたりが無難やないですか?」
メンバーの一人が発言した。それを別のメンバーが却下する。
「いくらふるさと納税頑張っても、誰も堅魚市には来てくれんですろう」
「だから施設の優待券とかを返礼品に入れればええやないですか?」
「わざわざ訪れたくなるような施設がうちにあるか? ないろう?」
堅魚市役所五階の会議室には南側に大きな窓があり、市の中心部──と言っても高層建物は皆無──の向こうには青々とした土佐湾が広がっている。沖合には養殖用のいけすが点在しており、その間を縫うようにして小型漁船が悠々と走っていた。
「係長、どうします?」
近くにいたメンバーに訊(き)かれ、奨吾は首を捻(ひね)った。
「うーん、難しいな」
発端となったのは民間の有識者で構成される人口戦略会議が今年の春に公表した内容だ。全国の自治体の持続可能性を分析したもので、一七二九の自治体のうち、七四四が消滅可能性自治体と認定された。若年の女性人口が減少していて、将来的に存続が危ぶまれる自治体のことだ。堅魚市も消滅可能性自治体として認定されていた。
あくまでも目安としてのものであり、高知県内においても半数以上の市町村が消滅可能性自治体となったのであるが、この調査に肝を冷やしたのがほかでもない、堅魚市長である永川彰浩(ながかわあきひろ)だった。もっとこの町の人口を増やさんとならん。そう思った彼はトップダウンで命じた。堅魚市に人を集める施策を立案せよ、と。そして白羽の矢が立ったのが商工観光課観光係の係長である奨吾だった。
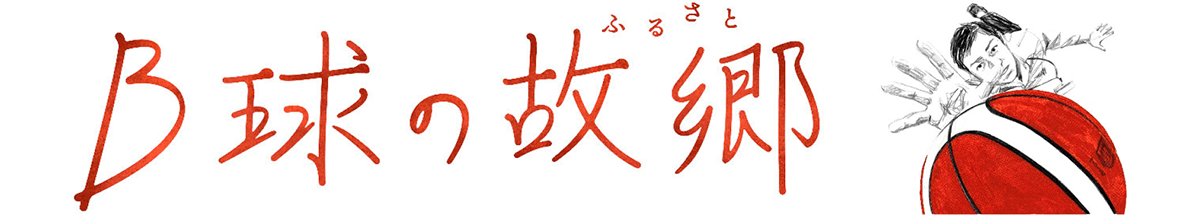
 ポストする
ポストする