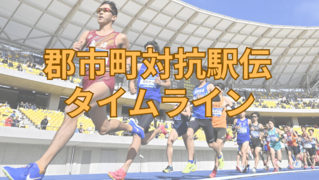子どもに無料または低額で食事を提供する子ども食堂の活動を後押しするため、県は「こども(地域)食堂サポートセンター」を設置した。子ども食堂は身近な地域で民間のボランティアや企業・団体によって自主的に運営されている。多世代交流の場として地域の活性化に貢献するともいわれる。センターを核に、子ども食堂に対する支援の輪が広がり、活動の充実につながることを期待したい。
子どもの貧困への関心の高まりに伴い、子ども食堂は2010年代半ばから県内でも広まってきた。運営形態はさまざまで、現在は貧困対策だけでなく子育て支援や孤立防止を目的に、対象者を制限せず、子どもからお年寄りまで地域全体に間口を開く食堂も増えている。
認定NPO法人全国こども食堂支援センター「むすびえ」(東京都)の調査(2023年度時点)によると、県内には101カ所の子ども食堂がある。小学校数に対する割合は24・4%で、全国35位という。同NPO法人の担当者は「まだ伸び代はある」と指摘する。
サポートセンターは県社会福祉協議会(宇都宮市)が県の委託を受け運営する。食堂の開設・運営に関する相談支援や情報提供、運営者と支援希望者の交流会、食品や寄付金の分配、支援をしたい企業・団体と支援を受けたい子ども食堂の仲介を行う。
中でも期待が大きいのは、支援の仲介であろう。宇都宮市が関係団体と2022年度に独自に始めた、子ども食堂などへの寄付や支援活動を仲介する取り組みでは、開始直後から寄付や支援を申し出る市民、団体が相次いだ。
ただ自治体によっては、こうした仕組みを作りたくても、規模的に難しいという声もあった。サポートセンターの開設によって、市町を越えた広域的な支援の仲介も可能になるはずだ。
子ども食堂の運営や啓発に取り組んできた県若年者支援機構の荻野友香里(おぎのゆかり)部長は「子どものために何ができるか対話を重ねていくことで、本当の意味で地域に開かれた場所となるよう、手を取り合っていくことが大切だ」と話す。
子どもが地域で安心して過ごせる場所を増やすためにも、サポートセンターは子ども食堂の啓発を進め、意欲ある運営者や協力者の掘り起こしにも努めてほしい。
 ポストする
ポストする