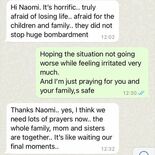イランのイスラエルへの報復攻撃、イスラエル軍とイスラム組織ハマスの泥沼化した戦闘、出口の見えないロシアとウクライナの戦争-。ある日突然、自国が攻撃にさらされる。そんな脅威が広がりつつある。
装甲車が前進し、重機関銃を撃ち続けた。大砲の砲撃。耳をつんざくような発射音と衝撃波が観覧席にも押し寄せた。
4月上旬、宇都宮市の陸上自衛隊宇都宮駐屯地。創立74周年記念行事で空砲による模擬戦が披露された。奪われた陣地を奪還する想定。そぼ降る雨の中、非日常の戦闘風景に来場者の視線がくぎ付けになった。
近くに住む下野市、会社員石川桂子(いしかわけいこ)さん(39)にとって自衛隊は身近な存在だ。模擬戦について「見たこともないような車両が登場し迫力があった」。一方、「怖さもあった。ウクライナのことがあるので、これが戦争なのかなと思った」とこぼした。
福島県郡山市から訪れた会社員竹松郁夫(たけまついくお)さん(58)は「自国が攻められた時に備え訓練は必要。巻き込まれないために自衛隊がいる」。そう考えを語った。
近年、安全保障を巡る政府の政策転換が続く。他国の領域内を攻撃できる反撃能力(敵基地攻撃能力)の保有、殺傷能力を持つ武器輸出の解禁、防衛費の増額-。不安定な海外情勢も相まって、日本国憲法が掲げる平和主義や9条が定める戦争の放棄、戦力不保持の変容を危惧する声もある。
1945年7月。米軍機が襲来し、620人以上が死亡した宇都宮空襲。その記録を発信し続ける市民団体「ピースうつのみや」の田中一紀(たなかかずのり)代表(82)は「武力行使を当然だと思うような社会風潮が横行している」と危機感を口にした。 憲法9条を「最後の歯止め」と強調する。「(他国の)脅威から、なし崩し的に憲法を変えるという議論はおかしい。平和国家として世界に訴え続けることが日本人に委ねられている」と話す。
若い世代も戦争と平和を直視している。宇都宮空襲関連のイベントを行ってきた学生サークルでサークル長を務めた宇都宮共和大4年藤田虎流(ふじたたける)さん(21)はウクライナ侵攻のニュースで、生まれて初めて空爆を目にした。その惨状が伝え聞いた宇都宮空襲と重なった。「防衛力は必要。でも、増強を繰り返すのは過去の過ちにつながる」と指摘する。武力衝突を避ける手段として「まずは国同士が対話するべきだ」と考える。
緊迫する国際情勢の中で、平和主義をどう守っていくのか。それぞれが課題と向き合い続けようとしている。
◇ ◇
日本国憲法は3日、施行から77年を迎える。国民の権利と自由を守る最高法規だが、日々の生活の中で憲法に触れ、考える機会は少ない。私たちにとって憲法とは。県民の姿や思いを通し意義や課題を見つめる。
 ポストする
ポストする