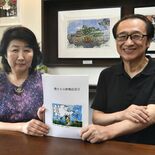太平洋戦争の終結から80年の節目を迎えた今年、下野新聞社はさまざまな平和報道を展開している。戦争体験者がわずかとなり、記憶を伝えることが年々難しくなる中、平和への願いを未来へどう継承していくか。15日に始まる新聞週間に合わせ、取材を担当した記者が抱いた思いを紹介する。

それは地元紙としての使命だったように思う。
1945年7月12日深夜から13日未明、県都を襲った宇都宮空襲。米軍の大型爆撃機B29による焼夷(しょうい)弾攻撃は下野新聞本社にも直撃し、社屋が燃え、社員が負傷した。13日付の下野新聞は休刊。「新聞特報」と呼ぶ一枚ペラの号外を配るだけで精いっぱいだった。
あの日、発行できなかった下野新聞を80年の時を経て発行しよう-。各部署から集まったメンバーが力を合わせ“空白の紙齢”を埋める形で今年7月12日、特別紙面を届けた。
全4面。1面は「宇都宮で大空襲」の大見出しと共に、当時伝えられなかった被害状況を詳報。4面は空襲直後の写真を並べ、一部は人工知能(AI)でカラー化。宇都宮市が米軍資料をひもとき、大規模に調査した戦災記録保存事業の記録などこの80年間、空襲の記憶を語り、受け継ぎ、記録してきた人たちの思いも紙面に刻んだ。
2、3面は地図。空襲体験者の話を体験場所ごとに記載した。これは記者の希望でもあった。
父母か祖父母が経験し、身近だった空襲体験は80年がたち、語れる人が少なくなった。ならば記憶をまちに刻もう、まちが語れるようにしよう-。次世代型路面電車(LRT)や新幹線が走る宇都宮。その昔、この路地で、この公園で、こんなにも悲しい出来事があったのだ、と。
新聞の大きな見開き紙面で視覚的に伝えること、それは新聞の特性を生かした伝え方でもあった。
だが、これが完成版ではない。発行後、これまで分かっていなかった犠牲者の記録を本紙が見つけ、620人以上とされた宇都宮空襲の死者数は、621人以上に塗り替えられた。正確な死者数は80年がたった今も分からないままだ。全てが明らかになった時、完成版を届けたい。
(宇都宮総局 瀬戸覚旨)

 ポストする
ポストする