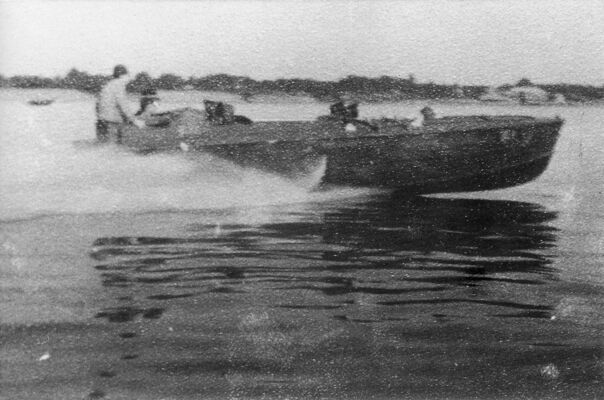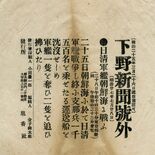1945年8月15日で太平洋戦争は終わった、はずだった。翌16日、高知県の香美郡夜須町(現香南市夜須町)で出撃準備をしていた特攻艇「震洋」が爆発する事故があり、111人の若い命が散った。
震洋は、「本土決戦」が叫ばれた戦争末期に旧海軍が開発した。ベニヤ板を組んだモーターボートに250キロもの爆弾を積み、敵艦に突っ込む。操縦者は二度と戻れない特攻兵器だった。
太平洋沿岸に配備され、夜須町には45年5月、25艇と160人の隊員が割り当てられた。全員が20歳前後の県外出身者。ボートを納める格納壕(ごう)を掘る作業には、地元住民も駆り出された。
隊員は民家に分宿していた。当時11歳の小松敏彦(こまつとしひこ)さん(91)=香南市夜須町手結山=は、下宿先ではなかった近くの叔母宅に3、4人が毎日のように食事や入浴に訪れる様子を見た。
「食べ物のない時代じゃった。けんど、地元の人はおもてなしをしよった。隊員も母親が恋しかったのかもしれんね」
残り:約 1045文字/全文:1487文字
この記事は「下野新聞デジタル」の
スタンダードプラン会員・愛読者(併読)プラン会員・フル(単独)プラン会員
のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

 ポストする
ポストする